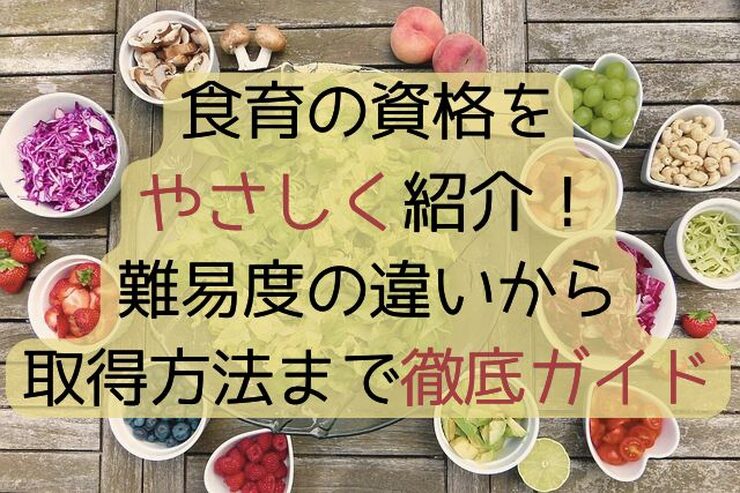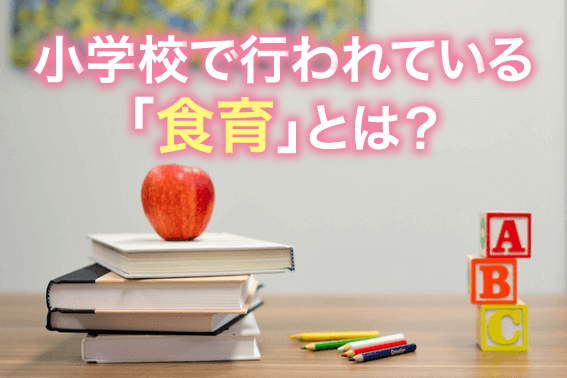子どもに食育を行う理由は?取り組み方とポイントを解説
記事更新日:2024年8月20日食育は、子どもたちの健全な成長と発達に欠かせない重要な要素です。
栄養バランスの取れた食事は、身体の健康を保つだけでなく、心の成長にも大きな影響を与えます。
さらに、食習慣や嗜好の形成、マナーや文化の理解も食育を通じて育まれます。
子どもに対する食育は、なぜ必要なのでしょうか。食育は、単に食事のしかたを子どもに教えるだけの教育ではありません。子どもは食をとおして、人間らしいさまざまな感覚や習慣を身につけていきます。食育はそれらを促し、子どもの成長を手助けする大きな役割を果たします。
そのため、食育はそのような効果を見据えて効果的に行うことが大切です。今回は、食育が必要な理由を説明するとともに、食育の取り組み方について解説します。

目次
食育が子どもたちに与える影響とその重要性
食育は、子どもたちの健康な成長と発達に欠かせない要素です。
心身の健全な発達を支え、食習慣や嗜好の形成に影響を与え、マナーや文化の理解を深める役割を果たします。
ここでは、具体的な影響とその重要性について詳しく解説していきます。
心身の発達における食の役割
食は、子どもたちの心身の発達に直接的な影響を与えます。
適切な栄養摂取は、成長期における体の発達を促進し、健康な生活を維持するために不可欠です。
栄養と身体の発達
子どもたちの成長には、バランスの取れた栄養が必要です。
例えば、カルシウムは骨の成長を促進し、タンパク質は筋肉や組織の発達に寄与します。
ビタミンやミネラルも、免疫力を高め、病気の予防に役立ちます。
これらの栄養素を適切に摂取することで、健康な身体が形成されます。
栄養と脳の発達
栄養は脳の発達にも深く関わっています。
オメガ3脂肪酸やビタミンB群は、脳の機能を高め、記憶力や集中力の向上に寄与します。
特に、DHA(ドコサヘキサエン酸)は神経細胞の構造を支える重要な成分であり、認知機能の発達に欠かせません。
これらの栄養素を含む食品を摂ることで、子どもたちの学習能力が向上します。
食習慣と嗜好の形成
子どもたちの食習慣や嗜好は、幼少期の経験によって大きく影響を受けます。
適切な食習慣を身につけることは、生涯にわたる健康維持に重要です。
幼少期の食体験の重要性
幼少期に経験する食体験は、子どもたちの食習慣の基礎を形成します。
多様な食品を試し、味覚を広げることで、偏食を防ぎ、バランスの取れた食生活を維持できます。
例えば、新しい野菜や果物を積極的に摂取する習慣をつけることで、成長期に必要な栄養素をバランスよく摂取できます。
家庭での食習慣の影響
家庭での食習慣は、子どもたちの食生活に大きな影響を与えます。
親が健康的な食生活を実践することで、子どもたちも自然とそれに倣うようになります。
例えば、家族で一緒に食事をする時間を大切にすることで、食事の楽しさを共有し、健康的な食習慣を身につけられます。
マナーと文化の学び
食育は、単に栄養摂取の方法を教えるだけでなく、食事を通じてマナーや文化を学ぶ重要な機会でもあります。
これにより、子どもたちは社会性や礼儀を身につけられます。
食事のマナーの習得
食事のマナーを学ぶことは、他者との円滑なコミュニケーションを図る上で重要です。
例えば、箸の正しい使い方や食事中の姿勢、食べ物に対する感謝の気持ちを表現する方法などを教えることで、子どもたちは基本的な礼儀作法を身につけられます。
文化の理解と尊重
食育を通じて、子どもたちは食文化の多様性を理解し、他者の文化を尊重することを学びます。
例えば、異なる地域や国の料理を体験することで、その文化や歴史についての理解が深まります。
これにより、子どもたちは他者への理解と尊重の気持ちを育めます。
家族や友人との絆の形成
食事を共にすることは、家族や友人との絆を深める大切な時間です。
食卓を囲んでコミュニケーションを取ることで、互いの関係が強化され、情緒の安定が図られます。
これにより、子どもたちは安心感を持って成長できます。
食育の継続的な実践の重要性
食育は一時的な取り組みではなく、継続的に実践することが重要です。
子どもたちの成長段階に応じて、適切な食育を行うことで、健康で健全な成長をサポートできます。
家庭、学校、地域社会が一体となって、食育の推進に努めることが求められます。
以上のように、食育は子どもたちの心身の発達に多大な影響を与えます。
適切な栄養摂取、食習慣の形成、マナーや文化の学びを通じて、子どもたちが健やかに成長し、豊かな人生を送るための基盤を築くことが可能です。
家庭や学校、地域社会での継続的な食育の推進が、未来の健康な社会を支えるために重要です。
年齢別に見る食育のアプローチ
子どもの成長段階に応じて、適切な食育のアプローチを行うことは非常に重要です。
乳児期から幼児期、そして小学生に至るまで、各年齢段階での食育の方法や目標は異なります。
以下では、各年齢段階に応じた食育の具体的な取り組み方について詳しく解説します。
乳児期の食育(0-2歳頃)
乳児期は、食育の基礎を築く最も重要な時期です。
この時期に適切な食事を提供することで、子どもたちの健康な成長を支えられます。
離乳食の導入と栄養バランス
離乳食は、生後6ヶ月頃から始めるのが一般的です。
離乳食を通じて、さまざまな食材を試し、味覚の幅を広げることが重要です。
初めはお粥や野菜のピューレから始め、徐々にタンパク質や脂質を含む食品を加えていきます。
栄養バランスを考慮し、鉄分やカルシウム、ビタミンを含む食材をバランス良く取り入れることが大切です。
手づかみ食べと自主性の育成
1歳を過ぎると、子どもたちは手づかみ食べを始めます。
手づかみ食べは、子どもの自主性を育む良い機会です。
さまざまな食材を触ったり、自分で食べたりすることで、食に対する興味や関心が高まります。
また、手先の器用さや食事の楽しさを学べます。
アレルギー対策
乳児期には食物アレルギーのリスクもあるため、慎重に新しい食材を試すことが重要です。
アレルギー反応が出やすい食品は、医師の指導のもとで少量ずつ試すことが推奨されます。
また、アレルギーの兆候が見られた場合は、直ちに専門医に相談することが必要です。
幼児期の食育(3-5歳頃)
幼児期は、食に対する好奇心が旺盛になり、自分の意見や好みを主張する時期です。
この時期に適切な食育を行うことで、健康な食習慣を身につけられます。
多様な食材の体験
幼児期は、さまざまな食材を体験させる良い時期です。
野菜や果物、魚や肉など、さまざまな食材を取り入れることで、子どもたちの味覚が豊かになります。
例えば、色とりどりの野菜を使った料理を一緒に作ることで、楽しみながら栄養を摂れます。
食事のマナー教育
この時期に食事のマナーを教えることは、社会性の育成にもつながります。
正しい箸の使い方や食事中の姿勢、感謝の気持ちを表す言葉などを教えることで、基本的な礼儀作法を身につけられます。
家族全員で食卓を囲む習慣をつけることで、食事の時間を楽しみながら学べます。
一緒に料理をする楽しさ
幼児期は、親と一緒に料理をする楽しさを体験させる絶好の時期です。
簡単な料理を一緒に作ることで、食材の選び方や調理方法を学べます。
例えば、サラダを作る際に野菜を洗ったり、フルーツを切るお手伝いをさせたりすることで、子どもたちの興味を引き出せます。
食べる楽しさを教える
幼児期は、食事の楽しさを教えることが重要です。
子どもたちが自分で食べる楽しさを感じられるように、食事の時間を楽しいものにする工夫が必要です。
例えば、子どもの好きなキャラクターの形に料理を作ることで、食事に対する興味を持たせられます。
小学生の食育(6-12歳頃)
小学生になると、子どもたちはより自立し、自分の意見や選択ができるようになります。
この時期に適切な食育を行うことで、生涯にわたる健康的な食習慣を身につけられます。
栄養バランスの理解
小学生には、栄養バランスの重要性を教えることが必要です。
学校の授業や家庭での食事を通じて、栄養素の役割やバランスの取れた食事の重要性を学びます。
例えば、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルがどのように体に影響を与えるかを具体的に教えることで、健康な食生活を意識するようになります。
自主的な食事の選択
この時期には、自分で食事を選ぶ機会が増えます。
親や教師は、子どもたちが健康的な選択をするためのガイドラインを提供することが重要です。
例えば、ファストフードやお菓子ばかりを選ぶのではなく、バランスの取れた食事を選ぶように促すことが必要です。
食事の計画と準備
小学生には、食事の計画と準備を手伝わせることが有効です。
週末の家族の食事を計画したり、買い物のリストを作成したりすることで、食事の準備に関与できます。
これにより、食事の重要性を理解し、自分で健康的な食生活を維持する力が養われます。
食材の選び方と調理方法
小学生になると、食材の選び方や調理方法をより具体的に教えられます。
例えば、買い物に一緒に行き、新鮮な野菜や果物の選び方を教えることで、食材に対する理解が深まります。
また、簡単な料理を一緒に作ることで、調理の基本を学ぶことも可能です。
以上のように、年齢別に見る食育のアプローチは、各段階で異なる目標と方法があります。
乳児期から始まる食育の基礎を築き、幼児期には多様な食材の体験やマナー教育、小学生には栄養バランスの理解と自主的な食事の選択を教えることで、子どもたちは健やかに成長し、豊かな人生を送るための基盤を築けます。
家庭や学校、地域社会での継続的な食育の推進が、未来の健康な社会を支えるために重要です。
年齢に応じたお手伝いのすすめ方とポイント
子どもにとって、家事や食事の準備を手伝うことは、自主性や責任感を育む重要な機会です。
年齢に応じた適切なお手伝いの方法を知ることで、子どもたちが楽しみながら家庭の一員としての役割を果たせます。
以下では、2~3歳頃、4~6歳頃、小学生以降の年齢別におすすめのお手伝いの方法とそのポイントについて詳しく解説します。
2 ~3歳頃のお手伝い
2~3歳頃の子どもは、興味や好奇心が旺盛で、新しいことに挑戦する意欲が高まります。
この時期に簡単なお手伝いを通じて、基本的な生活習慣や協力の精神を育めます。
簡単で安全なお手伝い
2~3歳の子どもには、安全で簡単なお手伝いを提供することが重要です。
例えば、以下のようなお手伝いが適しています。
食卓の準備
ナプキンやプラスチックの食器をテーブルに並べること。
片付け
おもちゃを決められた場所に戻すこと。
簡単な掃除
手拭きでテーブルを拭くこと。
これらのお手伝いは、子どもが達成感を感じながら学べる活動です。
褒めて伸ばす
この時期の子どもには、成功体験を通じて自信をつけることが大切です。
お手伝いをした際には、具体的に褒めることで、子どものモチベーションを高めます。
例えば、「テーブルをきれいに拭けてすごいね!」といった具体的なフィードバックを与えましょう。
お手伝いの習慣化
2~3歳の頃から、お手伝いを日常の習慣にすることは重要です。
毎日のルーチンにお手伝いを組み込むことで、自然と協力の姿勢が身につきます。
例えば、毎朝の食事の前にテーブルを拭く習慣をつけられます。
4 ~6歳頃のお手伝い
4~6歳頃の子どもは、手先が器用になり、より複雑なお手伝いに挑戦できます。
この時期には、責任感や達成感を育むためのお手伝いを提供することが重要です。
具体的なお手伝いの例
4~6歳の子どもには、以下のようなお手伝いが適しています。
野菜の洗浄
野菜を洗うことで、料理の準備に参加できます。
テーブルのセッティング
食器やカトラリーを正しい位置に並べること。
簡単な料理の手伝い
サンドイッチを作る、フルーツを切るなどの簡単な料理を手伝うこと。
これらのお手伝いを通じて、子どもたちは家庭の一員としての役割を学びます。
教育的なアプローチ
4~6歳の子どもには、なぜお手伝いが重要なのかを教えることが効果的です。
例えば、「野菜を洗うときれいになって、おいしく食べられるんだよ」といった説明をすることで、子どもたちの理解を深められます。
安全と衛生の教育
この時期には、安全と衛生の基本も教えることが重要です。
例えば、包丁の使い方や手の洗い方を正しく教えることで、事故を防ぎます。
お手伝いを通じて、基本的な安全と衛生の知識を身につけられます。
小学生以降のお手伝い
小学生になると、子どもたちはさらに高度なお手伝いに挑戦できます。
この時期には、自主性やリーダーシップを育むための活動を提供することが重要です。
具体的なお手伝いの例
小学生には、以下のようなお手伝いが適しています。
料理の手伝い
野菜のカット、簡単な料理の作成など、実際に料理に参加すること。
洗濯物の取り込みと畳み
洗濯物を取り込み、畳んで収納すること。
掃除の手伝い
部屋の掃除、ゴミの分別など、家庭の維持に関わるお手伝い。
これらのお手伝いは、子どもたちが責任感を持ち、自分でできることの範囲を広げる助けとなります。
チームワークと協力の精神
小学生には、家族全員で協力することの大切さを教えることが重要です。
家族全員で掃除の日を設けたり、料理を一緒に作る時間を設けたりすることで、協力の精神を育めます。
お手伝いの計画と実行
小学生には、自分でお手伝いの計画を立てることを促します。
例えば、週末の家事の計画を立てたり、自分の役割を決めたりすることで、主体的に行動する力を養います。
また、計画通りに実行することで、達成感を感じられます。
お手伝いを通じた学び
小学生のお手伝いには、多くの学びの機会が含まれています。
例えば、料理を通じて計量や時間管理のスキルを学び、掃除を通じて整理整頓の重要性を理解します。
これらの学びは、学校での勉強にも役立つスキルです。
年齢に応じたお手伝いのすすめ方とポイントを理解することで、子どもたちの自主性や責任感を育めます。
2~3歳頃から始めるお手伝いは、生活習慣の基礎を築き、4~6歳頃には協力の精神と基本的なスキルを学び、小学生以降には自主性とリーダーシップを育むことが可能です。
家庭での継続的なお手伝いの実践は、子どもたちの成長にとって重要な役割を果たします。
以上のように、年齢に応じたお手伝いのすすめ方とポイントを理解し、実践することで、子どもたちは家庭の一員としての役割を果たしながら成長できます。
2~3歳頃の簡単なお手伝いから始まり、4~6歳頃にはより複雑なお手伝いに挑戦し、小学生以降には自主性とリーダーシップを育む活動に参加することで、子どもたちの心身の成長を支えられます。
家族全員で協力しながら、お手伝いの楽しさと大切さを共有することが、子どもたちの未来に繋がる重要なステップです。
食育を始める最適なタイミング
食育は、子どもの健康な成長と発達に欠かせない重要な要素です。
食育を始めるタイミングを適切に見極めることで、子どもたちが健やかに育つための基盤を築けます。
ここでは、食育を始める最適なタイミングとその方法について詳しく解説していきます。
食育の基礎を築く乳児期
食育の第一歩は、乳児期から始まります。
この時期は、子どもの健康な発育のために適切な栄養を摂取することが最も重要です。
乳児期の食育は、将来的な食習慣の形成にも大きな影響を与えます。
母乳育児とミルク育児の役割
乳児期の食育は、母乳育児やミルク育児から始まります。
母乳は、赤ちゃんに必要な栄養素をバランスよく含んでおり、免疫力の向上にも寄与します。
また、母乳を通じて、母親との絆が深まり、情緒の安定にもつながります。
母乳が難しい場合は、ミルク育児を通じて適切な栄養を補うことが重要です。
離乳食の開始
生後6ヶ月頃から始まる離乳食は、食育の重要なステップです。
この時期にさまざまな食材を試し、食感や味覚の幅を広げることが大切です。
初めはお粥や野菜のピューレから始め、徐々に固形物やタンパク質を含む食材を取り入れていきます。
離乳食を通じて、食事の楽しさや食材の多様性を学びます。
幼児期の食育の始め方
幼児期は、食に対する好奇心が芽生え、食事の重要性を理解し始める時期です。
この時期に食育を始めることで、健康的な食習慣を身につける基盤を築けます。
家族と一緒に食事をする習慣
幼児期の食育の一環として、家族と一緒に食事をする習慣をつけることが重要です。
家族との食事は、食事の楽しさを共有し、正しい食事マナーを学ぶ場となります。
また、食事を通じて親子のコミュニケーションが深まり、情緒の安定にも寄与します。
食事の手伝いをさせる
幼児期には、子どもに簡単な食事の手伝いをさせることが効果的です。
例えば、野菜を洗ったり、テーブルのセッティングを手伝ったりすることで、食事の準備に興味を持たせられます。
これにより、食材に対する関心が高まり、食育の効果がさらに高まります。
多様な食材の体験
幼児期は、さまざまな食材を体験させる良い時期です。
色とりどりの野菜や果物、魚や肉など、さまざまな食材を取り入れることで、子どもの味覚が豊かになります。
また、新しい食材に挑戦することで、偏食を防ぎ、バランスの取れた食生活を維持する習慣が身につきます。
食育を継続するためのポイント
食育は一時的な取り組みではなく、継続的に実践することが重要です。
子どもの成長段階に応じて、適切な食育を行うことで、健康で健全な成長をサポートできます。
家庭、学校、地域社会が一体となって、食育の推進に努めることが求められます。
家庭での継続的な取り組み
家庭での食育は、日常の生活の中で自然に行われることが理想です。
毎日の食事を通じて、バランスの取れた食事の重要性や食材の多様性を教えられます。
例えば、家族で一緒に料理をする時間を設けることで、食に対する興味や関心を引き出せます。
学校での食育プログラム
学校は、子どもたちが集団生活を通じて学ぶ場であり、食育においても重要な役割を果たします。
学校での食育プログラムは、子どもたちが健康的な食習慣を身につけるための貴重な機会となります。
栄養教育の授業や給食の時間を通じて、バランスの取れた食事の重要性を教えられます。
地域社会での食育活動
地域社会での食育活動も重要です。
地域のイベントやワークショップを通じて、子どもたちが食に対する興味や関心を深められます。
例えば、地域の農家を訪れたり、地元の食材を使った料理教室に参加することで、食育の実践を学べます。
子どもにとって食育が大切な理由

子どものころの食体験は、その後の人生に大きな影響を与えます。そのため、食育の実践は、子どもにとってとても重要なことです。まずは、その理由について見ていきましょう。
食と心身の成長との関係
幼少期の食に関する体験は、心身の成長と密接に関係しています。食べ物は身体を作るだけでなく、心の発達にも大きな影響を与えます。たとえば、家族や仲間と一緒に食事をして、「おいしい」という感覚を共有することは、感情を豊かにして情緒を安定させる効果があると言われています。
嗜好や食習慣の決定
人の嗜好や食習慣は、幼少期に決まると言われています。そのため、子どもは幼少期のうちからしっかりと食育を受けることで、より豊かな食の感覚を身につけ、大人になってからもそれに基づく健康的な食生活を送ることができるようになります。
マナーの習得や文化の理解
食に関するマナーを学び、文化を理解することは、人間的な成長には必要不可欠だと言えるでしょう。子どもの社会性を育てるためには、食に関わるすべてのものに感謝するという考え方を教えることも大切です。
年齢別の食育への取り組み方
つぎは、子どもの年齢に合わせた食育の取り組み方について紹介します。子どもは年齢によって、食をとおしてさまざまなことを学びながら成長していきます。食育は、子どもの健やかな成長にとってとても重要な役割を果たします。
乳児期(0-2歳頃)
子どもが健全な食生活を送るためには、乳児期から食育に取り組む必要があります。この頃の経験は、子どもの生活習慣の基礎となります。子どもは生まれたばかりの時期に母乳を飲む経験をすることで、人肌の心地よさを感じ、人を信頼する気持ちや愛する心を育むことができます。 また、離乳食を食べるようになったら、味覚を中心とした五感を養うことを意識することが大切です。さまざまな食材を使って味付けを工夫することで、子供の感覚を刺激します。子どもが自発的に手づかみで食べようとするときは、それを手助けしてあげましょう。「食事は楽しい」という経験をたくさんさせることに重きを置いてください。
幼児期(3-5歳頃)
幼児期は、栄養のバランスが取れた食事を規則正しく食べる習慣や味覚の基礎ができる時期です。家族や仲間と一緒に楽しみながら食事をし、そのなかでさまざまなことを学びます。しっかり体を動かして「お腹がすいたら食事をする」という生活リズムを確立するとともに、好き嫌いをせず何でもよく噛んで食べることが重要であることを理解します。 また、この頃に基本的な食事のマナーを覚えることも重要です。箸やスプーンの使い方、食事をするときの座り方、「いただきます」「ごちそうさま」といったあいさつについて、きちんと指導しましょう。
小学生(6-12歳頃)
小学校に入学したあとは、健康を促す基本的な食習慣を身につける時期です。この頃の食習慣は大人になってからの食習慣にそのまま反映されることが多いため、非常に大切な時期です。自己管理を行う力を養い、自分で自分をコントロールすることを覚えながら、健康な食生活について実践的に学んでいきます。規則正しい1日3食の食生活を維持し、マナーを守って食事をすることを習慣化しましょう。 また、「食べ残しをするのはもったいない」という気持ちを育てることも大切です。そのためには、自分で食べる食品は自分で選び、調理も自分で行う体験をさせることが有効です。食べ物について深く知ることで食べ物に対する興味を高めることがポイントとなります。
子どもにおすすめのお手伝いとポイント

食育では、食べ物に対する子どもの興味を高めることが重要です。そのためには、料理を子どもに手伝わせることがおすすめです。ただし、小さい子どもをキッチンに立たせるのは不安だと思う方も多いかもしれません。そこで、子どもの年齢に合わせたお手伝いの方法について紹介します。
2~3歳頃
2~3歳頃の子どもでも、内容を工夫すれば楽しみながらお手伝いをすることができます。遊びやその延長としてできる、手を使った作業をさせてあげましょう。必ず手本を見せながら一緒に作業を行ってください。 たとえば、柔らかい葉物の野菜や豆腐をちぎらせるという作業なら、とても簡単ですし安全です。たとえ子どもが失敗をしたとしても、むやみに怒ってはいけません。子どもなかの「料理は楽しい」という思いを育てることを優先しましょう。
4から6歳頃
4歳になれば包丁を使う作業もできるようになります。必ず一緒に作業を行い、見守りながら行うようにすれば問題はありません。けがをしにくいように設計された子ども用の包丁も販売されているため、心配な場合はこれを使うとよいでしょう。このような包丁は、キャラクターがついているなどデザインが子ども向けで可愛らしいものが多いため、子どもが料理に興味をもつきっかけとなるかもしれません。豆腐や練り物など、柔らかくて切りやすい食材から挑戦させるのがおすすめです。
小学生以降
小学生以上になったら、簡単な一品料理を完成させることを目指しましょう。味噌汁や目玉焼きなど何でもOKです。ただし、もちろん一度にすべてを完璧にこなせるわけではないため、子どもが失敗しても怒ったり、ネガティブな感想を伝えたりしてはいけません。励ましたり、上手にできたポイントをあげて褒めたりすることで、子どもが自発的に努力を重ねられるような状況を作ってあげることが大切です。
始めるタイミングはいつが良いか
料理のお手伝いをはじめるタイミングはいつでも構いません。子どもが料理をすることに興味を示すタイミングを見逃さないようにして、後押しすることが大切です。「うまくできるとは限らない」ということを前提に、子どものチャレンジを応援するような態度を意識しましょう。 食育という観点から言えば、子どもにお手伝いを無理に押し付けるのはNGです。どうしても子どもに料理を手伝わせたい場合は、まずは子どもが料理に興味をもつような働きかけを行うのがおすすめです。ささいなことでも構わないので、子どもとの会話のなかで食べ物や料理など食に関する話題を増やしてみてください。親が料理をしている姿を、子どもに見せることも有効です。
食育で子どもの成長を見守ろう

食育は、子どもの健やかな成長のために無くてはならないものです。食をとおしたさまざまな体験は、大人になってからの食習慣にも大きな影響を与えます。そう考えると、子どもにとってベストな食育を行いたいですよね。
食育の効果を十分に発揮するためには、子どもの感情を尊重し、それに合わせて行うことが大切です。子どもが「食べ物を食べること」を肯定的に捉え、興味を持つことができるように手助けをしてあげましょう。
まとめ
子どもの健全な成長には食育が欠かせません。
食育は、栄養バランスの取れた食事を通じて身体の健康を保ち、心の成長にも大きな影響を与えます。
また、幼少期の食体験や家庭での食習慣を通じて、食に対する興味や嗜好が形成されます。
さらに、食事のマナーや食文化の理解は、社会性や礼儀の習得にもつながります。
家庭や学校、地域社会が一体となって継続的に食育を推進することが、子どもたちの健康で豊かな人生の基盤を築くために重要です。
- 通信講座のSARAスクール編集部
-
心理カウンセラー資格やリンパケアセラピスト等の体系資格、食育資格などを扱うSARAスクール編集部が運営するコラムです。主に女性向けのキャリアアップやスキル習得を目的とした講座が多く、家事や育児と両立しながら学べる環境が整っています。資格取得を目的とした講座も充実しており、仕事や日常生活に活かすことが可能です。