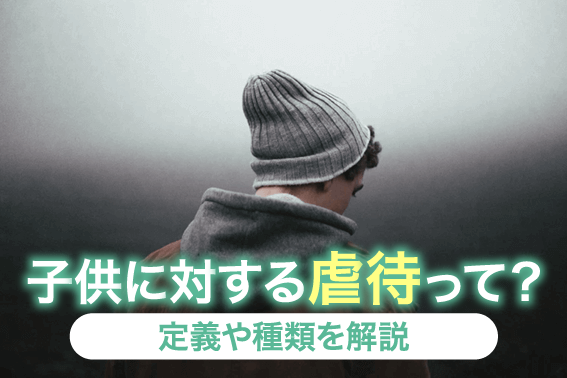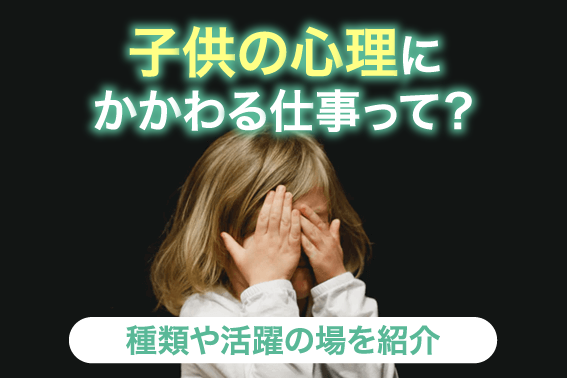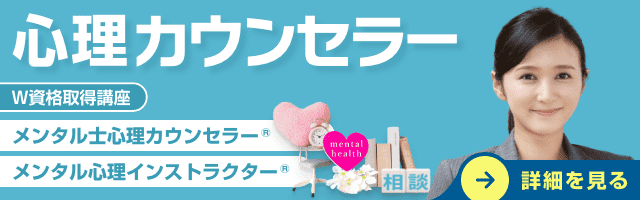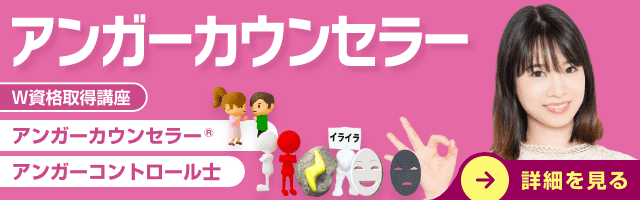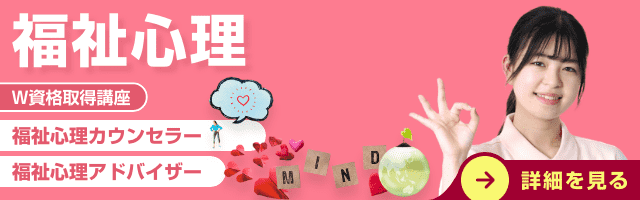小学校高学年の心理と特徴とは?親が知っておくべき成長と変化
記事更新日:2024年7月22日小学校高学年の子どもは、心身がともに大きく成長しています。とくに、反抗期などを迎えるため、子どもの気持ちが理解できないと悩む親はとても多いです。小学校高学年の子どもはどのような心理になっているのでしょうか。
小学校高学年の子どもとうまく付き合うには、子どもの心理状態をしっかりと押さえておくことが重要です。そこで、今回は小学校高学年の子どもの心理の特徴について説明します。特徴をしっかりととらえて、子どもに上手に接することができるようにしましょう。
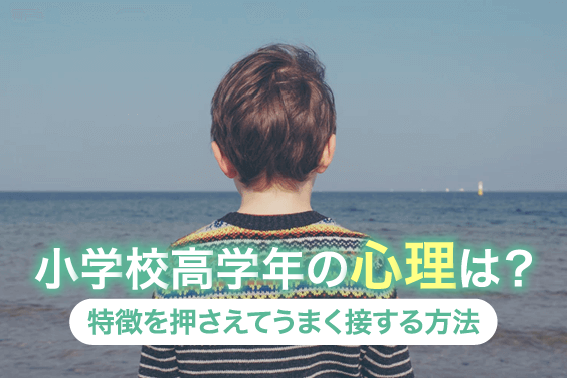
目次
小学校高学年の心身の成長
小学校高学年は、子どもたちにとって大きな転換期です。身体的な成長だけでなく、知性においても大きな変化が訪れます。子どもたちの成長について理解を深めることで、より適切な関わり方を見出すことができるでしょう。
身体的な成長と変化
小学校高学年になると、子どもたちの体には顕著な変化が現れ始めます。特に男女の性差が明確になってくる時期でもあります。
女子の場合、多くの子が初経を迎えます。小学校高学年で初経を経験する女子は半数以上に上ります。また、胸の膨らみが目立ち始め、女性らしい体つきへの変化が始まります。
一方、男子の場合は精通を経験する子もいます。また、身長が急激に伸び始め、男性らしい体格へと変化していきます。
こうした身体的変化は、子どもたちに戸惑いや不安をもたらすこともあります。親としては、こうした変化が自然なものであることを伝え、子どもの気持ちに寄り添うことが大切です。
知的能力の発達
小学校高学年になると、子どもたちの知的能力も飛躍的に発達します。この時期の特徴として、以下のようなことが挙げられます。
・抽象的思考の発達
具体的な事象だけでなく、抽象的な概念を理解し、考えることができるようになります。
・論理的思考の向上
因果関係を理解し、論理的に物事を考えられるようになります。
・批判的思考の芽生え
周囲の意見や情報を鵜呑みにせず、自分なりに考え、判断する力が育ちます。
・長期的な計画立案
将来のことを考え、目標に向けて計画を立てる能力が身につきます。
これらの能力の発達により、子どもたちはさまざまな課題に対して、より主体的に取り組めるようになります。しかし、同時に自分の能力と現実とのギャップに悩む子どもも出てくるため、親の適切なサポートが必要です。
小学校高学年の心理的特徴
身体的な成長と知的能力の発達に伴い、小学校高学年の子どもたちの心理面にも大きな変化が訪れます。この時期の心理的特徴を理解することで、子どもたちの行動や態度の背景にある思いを汲み取ることができるでしょう。
学童期の終わり、青年期の始まり</h3
小学校高学年の時期はエリクソンの発達段階では、学童期から青年期への移行の段階にあたります。子どもたちは、学童期で培った能力を基盤に、新たな課題に直面していきます。
学童期は、子どもが小学校に通う期間であり、学校で知識を身につけ、学習する機会が多い時期です。この時期の心理的課題は「勤勉性」の獲得です。子どもたちは、自ら学んで物事を完成させたり、仲間と集団行動をして成功したりする体験を通して、自分が有能であると感じ、自尊心を得ていきます。
青年期に入ると、子どもたちは「自分がどんな人間で、何者であるのか」と思い悩み、自分の「アイデンティティ」を探し始めます。アイデンティティを確立できると、自分の価値観を信じて応えようとする忠誠心が芽生えます。しかし、この時期に自分が何者か確立できないと、「同一性拡散」という状態になり、社会で活躍することが難しくなる可能性があります。
自立心と反抗心の芽生え
小学校高学年になると、子どもたちは自立心を強く持つようになります。これまで親に頼っていたことを自分でやろうとする姿勢が見られるようになります。しかし、同時に自立心が反抗心としても表れることがあります。
親の言うことに素直に従うのではなく、自分の意見を主張したり、親の指示に反発したりする場面が増えてくるでしょう。これは子どもが自我を確立していく過程であり、健全な成長の一部と言えます。
ただし、この反抗心が強すぎると、親子関係に軋轢が生じる原因にもなります。親としては、子どもの自立心を尊重しつつも、適切な境界線を設けることが重要です。子どもの意見に耳を傾けながらも、社会のルールや家庭の決まりについては毅然とした態度を示す必要があります。
友人関係の重要性の高まり
小学校高学年になると、友人関係がより重要になってきます。この時期の子どもたちにとって、友達との関係は自己形成や社会性の発達に大きな影響を与えます。
特に、同性の友達とのグループ形成が顕著になります。グループ内での共通の趣味や関心事を通じて、仲間意識を深めていきます。この過程で、協調性や他者への思いやりといった社会性を学んでいきます。
小学校高学年の時期に
小学校高学年は、自己肯定感と劣等感が形成される重要な時期です。この時期の経験が、子どもたちの将来的な自己イメージや自信に大きな影響を与えます。
自己肯定感を育む
自己肯定感は、自分自身を価値ある存在として認識し、自分の能力や可能性を信じる気持ちです。小学校高学年の時期に、適度な成功体験や周囲からの肯定的な評価を得ることで、健全な自己肯定感が育まれます。
自己肯定感が高い子どもは、新しい挑戦に積極的で、失敗を恐れずにチャレンジする傾向があります。また、ストレスへの耐性も高く、困難な状況に直面しても前向きに取り組むことができます。
親としては、子どもの努力や成果を適切に評価し、励ましの言葉をかけることが大切です。ただし、過度な褒め言葉や期待は、かえって子どもにプレッシャーを与えてしまう可能性があるため、バランスの取れた関わり方が求められます。
劣等感への対処
一方で、この時期は劣等感が芽生える時期でもあります。学業成績や運動能力、容姿など、様々な面で友達と比較することで、自分の不足を強く意識するようになります。
劣等感は必ずしも悪いものではなく、自己改善のモチベーションになることもあります。しかし、過度の劣等感は自信の喪失や消極的な態度につながる可能性もあり注意が必要です。
親としては、子どもの個性や長所に目を向け、それを伸ばす機会を提供することが大切です。また、失敗や挫折を経験した際には、その経験から学ぶことの大切さを伝え、前向きな姿勢を育むよう支援しましょう。
学習への態度
学童期の終わりから青年期の始まりにかけて、学習に対する態度も変化します。単純な暗記や反復学習から、より抽象的な思考や問題解決能力が求められるようになります。
この変化に適応できるかどうかが、その後の学習意欲や学業成績に大きく影響します。
家族関係の変化と自立への欲求
親からの自立への欲求が強まるのもこの時期の特徴です。それまで絶対的な存在だった親の言動に疑問を持ち始め、反発することも増えてきます。こうした変化は、親子関係に緊張をもたらすこともありますが、子どもの自立に向けた重要なプロセスでもあります。
一方で、まだ完全な自立は難しく、親の支えを必要とする部分も多く残っています。この「依存と自立の葛藤」が、青年期の始まりを特徴づける重要な要素となります。
思考力と能力のギャップ
小学校高学年になると、子どもたちの思考力は飛躍的に発達します。しかし、その一方で実際の能力や経験がまだ追いついていないことも多く、こうしたギャップが子どもたちに戸惑いや挫折感をもたらすことがあります。
抽象的思考の発達と現実とのギャップ
この時期の子どもたちは、より複雑な概念を理解し、抽象的な思考ができるようになります。しかし、思考力に比べて実際の問題解決能力や経験が不足していることがあります。
例えば、ある課題に対して理論的には解決策を考えつくことができても、実際にそれを実行に移す段階で困難に直面することがあります。これは、思考力と実践力のギャップによるものです。
このギャップは、子どもたちに挫折感や自信の喪失をもたらす可能性があります。親としては、子どもの思考力を褒めつつも、実践には時間と努力が必要であることを伝え、粘り強く取り組む姿勢を育むことが大切です。
理想と現実のバランス
小学校高学年の子どもたちは、理想を追い求める傾向が強くなります。完璧主義的な考え方が芽生え、自分や他人に高い基準を求めることがあります。しかし、現実の世界では理想通りにいかないことも多く、このギャップに悩む子どもも少なくありません。
親としては、理想を持つことの大切さを認めつつも、現実世界との折り合いをつける方法を教えることが重要です。失敗や挫折を恐れずにチャレンジすることの大切さ、そして失敗から学ぶことの価値を伝えましょう。
また、「完璧」を求めるのではなく、「ベストを尽くす」ことの意義を教えることで、より健全な目標設定と自己評価の姿勢を育むことができます。
道徳観と価値観の形成
小学校高学年は、道徳観や価値観が形成される重要な時期です。この時期に培われた価値観は、将来の人格形成に大きな影響を与えます。
「良い」「悪い」の判断力
小学校高学年になると、子どもたちは「良い」「悪い」の判断をより明確にできるようになります。単純に大人の言うことに従うのではなく、自分なりの価値基準で物事を判断しようとします。
この時期の子どもたちは、正義感が強く、公平性や平等性に敏感です。しかし、まだ経験や知識が不足しているため、時として極端な判断をしてしまうこともあります。
親としては、子どもの判断力を尊重しつつも、さまざまな視点から物事を見ることの大切さを教えることが重要です。また、道徳的なジレンマを含む事例について一緒に考え、議論することで、より深い道徳観を育むことができるでしょう。
社会規範の内在化
小学校高学年になると、社会規範をより深く理解し、内在化していく時期でもあります。法律や学校のルールなどの明文化された規則だけでなく、暗黙の了解や社会的マナーなども理解し、実践しようとします。
この過程で、時として規則に対する疑問や反発が生じることもあります。これは単なる反抗ではなく、社会規範を自分なりに消化し、内在化していく過程の一部と言えます。
親としては、規則の背景にある理由や意義を説明し、子どもが自発的に規範を受け入れられるよう導くことが大切です。また、家庭内でのルール作りに子どもを参加させることで、規範意識をより実践的に育むことができるでしょう。
小学校高学年におけるいじめの問題と対策
小学校高学年は、いじめの問題が顕在化しやすい時期です。この時期の子どもたちは、仲間集団の形成と共に、集団内での同調圧力が強まる傾向が見られます。特に、小学校後半から形成されるギャンググループや、中学校の時期に形成されるチャムグループでは、友達に合わせることへの圧力が著しく高くなるのが特徴的です。
このような集団の中で、仲間からの排除やいじめが行われることがあります。いじめの背景には、集団への服従を強化するという心理的メカニズムが働いていることが多いです。
いじめの形態も、子どもたちの特性を反映して変化していきます。直接的な暴力や暴言だけでなく、仲間はずれやSNSを利用した誹謗中傷など、より陰湿な形態のいじめが増加する傾向にあるのです。これらのいじめは発見が難しく、被害者の心に深い傷を残す可能性が高いと言えるでしょう。
いじめへの防止と対策
親や教師として、このようないじめの問題にどのように対応すべきでしょうか。まず重要なのは、子どもたちの様子を気にかけて、変化に気づくことです。突然の性格の変化や、学校に行きたがらない様子などは、いじめの兆候かもしれません。
また、子どもたちが安心して相談できる環境を整えることも大切です。いじめられている子どもは、周囲に相談することを躊躇する傾向があります。親や教師は、子どもが何でも話せる雰囲気づくりを心がけ、定期的にコミュニケーションを取ることが重要です。
さらに、いじめの予防教育も効果的です。思いやりの心や他者への共感能力を育む教育活動を通じて、いじめの加害者になる可能性を減らすことができます。また、傍観者にならず、いじめを見かけたら適切に対応する勇気を持つことの大切さを教えることも重要です。学校と家庭の連携も、いじめ対策には欠かせません。定期的な情報交換を行い、子どもの様子や学校での取り組みについて共有することで、より効果的な対策を講じることができます。
親子関係の変化
小学校高学年になると、親子関係にも変化が訪れます。子どもの自立心の芽生えと共に、これまでとは異なる関わり方が求められるようになります。
子どもの自立を促す関わり方
この時期の子どもたちは、自分で決定し、行動したいという欲求が強くなります。親としては、子どもの自立心を尊重しつつも、適切な指導と見守りのバランスを取ることが重要です。
例えば、日常生活の中で子どもに任せられる責任を徐々に増やしていくことで、自立心を育むことができます。宿題の管理や身の回りの整理整頓など、小さなことから始めて、徐々に範囲を広げていくのが良いでしょう。
ただし、全てを任せきりにするのではなく、困ったときには相談できる環境を整えることも大切です。子どもが自立心を持ちつつも、必要なときには助けを求められる関係性を築くことが理想的です。
コミュニケーションの変化への対応
小学校高学年になると、子どもとのコミュニケーションの取り方も変化します。これまでのように、親が一方的に指示や助言をするのではなく、子どもの意見を聞き、対話を通じて理解を深めていく姿勢が重要になります。
特に、子どもが悩みや不安を抱えているときは、すぐに解決策を提示するのではなく、まずは子どもの気持ちに寄り添い、共感的に聴く姿勢が大切です。子ども自身が自分の気持ちを整理し、解決策を考えられるよう、適切な質問を投げかけるなどのサポートをしましょう。
また、この時期の子どもたちは、親に話したくないことや秘密を持ち始めます。これは自我の発達の一環であり、ある程度は尊重する必要があります。ただし、深刻な問題を抱えていないかどうかを見極める洞察力も親には求められます。
学習面での変化と支援
小学校高学年になると、学習内容がより高度になり、学習への取り組み方も変化します。この時期の子どもたちの学習面での特徴を理解し、適切な支援を行うことが重要です。
学習内容への適切なサポート
小学校高学年では、抽象的な概念や複雑な問題解決能力が求められる学習内容が増えてきます。特に算数や理科などの教科では、論理的思考力や分析力が必要となります。
子どもによっては、急激な難易度の上昇に戸惑い、学習意欲の低下につながることもあります。親としては、子どもの学習状況を把握し、必要に応じて適切なサポートを行うことが大切です。具体的には、以下のような支援が考えられます。
・基礎的な学習内容の復習を促す
・学習計画の立て方をアドバイスする
・分からないことがあれば、遠慮なく質問するよう励ます
・必要に応じて、家庭教師や学習塾の利用を検討する
自主学習能力の育成
小学校高学年は、自主的に学習に取り組む姿勢を身につける重要な時期です。この時期に培われた学習習慣は、中学校以降の学習にも大きな影響を与えます。
親としては、子どもの自主性を尊重しつつ、効果的な学習方法を一緒に考えることが大切です。例えば、以下のようなアプローチが考えられます。
・時間管理の方法を教える(例:タイマーを使った集中学習)
・学習環境の整備を一緒に行う
・子どもの興味関心に合わせた学習教材を提供する
・学習の成果を認め、適切に褒める
ただし、過度に学習を強制したり、結果にこだわりすぎたりすることは避けましょう。子ども自身が学ぶ楽しさや達成感を味わえるよう、サポートすることが重要です。
小学校高学年の心理を学びたい方へ
小学校高学年の子どもの心理や特徴について、より深く学びたいと考えている方には、専門的な資格の取得がおすすめです。例えば、日本インストラクター技術協会の子供心理カウンセラー®(チャイルド心理資格)や日本メディカル心理セラピー協会【JAAMP】が認定するチャイルド心理カウンセラー®資格の受講も有効です。
これらの資格では、子どもの発達段階や心理特性について体系的に学ぶことができ、より適切な子育てや教育支援に役立つ知識とスキルを身につけることができます。
小学校高学年の心と体
小学校の高学年の子どもの心や体は、どのような状態にあるのでしょうか。小学校高学年は心と体が飛躍的に成長する時期であり、とても複雑な時期です。よって、しっかりと状態を理解することが重要です。
体が大人へと変化していく
小学校の高学年になると、体に大きな変化がおこります。特に男女の性差が顕著にあらわれてきます。まず、女子の場合は生理が始まる子どもが多くなります。小学校の高学年で生理がくるのは、過半数以上だといってもよいでしょう。また、少しずつ胸が膨らんできて、女性らしい体つきになる準備が始まります。それに対して男子の場合は、早い子であれば精通するようになります。加えて、身長が急激に伸び始め、男性らしい体に変化していくでしょう。
知的な興味を沸き始める
小学校高学年になると、心にも大きな変化があらわれてきます。 たとえば、推理的思考ができるようになり、さまざまなことを自分で考えて解決できるようになっていくでしょう。また、価値観が育ち、自分だけで意思決定ができるようになっていきます。さらに、想像意識も養われて、さまざまなものごとについて理解できるようになります。
小学校高学年の心理状態
小学校高学年の子どもの心理状態は、具体的にどのような状態なのでしょうか。難しい時期であるため、小学校高学年の子どもについて理解するには、細かいところまでしっかりと理解するようにしなければなりません。ここでは、小学校高学年の子どもの心理状態について基本的なところを説明します。
自立やそれに伴う反抗
小学校高学年になると交友関係が広がります。そのため、親よりも友人と遊ぶことが増えるでしょう。また、自立心も芽生えてくるので、親に干渉されたくないという気持ちも高まっていきます。そのため、親に少しでも指示や命令を出されると、強い反抗を見せることが多いです。親への反抗心から秘密をもつようになる可能性もあります。子どもが小学校高学年になったら、無理に子どもと一緒に過ごすのではなく、自発的な活動を見守るという姿勢をもつことが大切です。
自己肯定感や劣等感がうまれる
小学校高学年になれば、自分で仲間を作るようになります。学校のクラスや部活、習い事など、さまざまな場所でいろいろな人間関係を学んでいきます。そのなかで自分にとって良いと思える人間関係を築くことにより、自己肯定感もうまれるでしょう。ただし、その反面、仲間割れや仲間はずれが生じることもあります。そうなると、逆に劣等感につながることもあります。人間関係のなかで受ける影響は意外と大きなものとなります。人間関係がうまくいっていないと心配になりますが、子どもの様子を見つつ見守ることが大切です。仮に手を差し伸べるとしても、子どもの自尊心を傷つけないようなやり方を考える必要があります。
思考力と能力の違い
小学校高学年になると、判断力や推理力は大人にかなり近づきます。その反面、まだ能力はそれほど高くないため、仮説を立てて実践してもなかなかうまくできないことが多いです。そのため、成果が出ないことに落胆し、自暴自棄になってしまうこともあります。そのような姿を見ても、親は子どもを信じることが大切です。挫折から立ち直る姿を見守って支えてあげることで、子どもの大きな成長を促すことも可能になるでしょう。
「良い」「悪い」の分別がつく
小学校高学年には、 子どもとはいえ「良い」「悪い」の分別がしっかりつくようになります。良いことをしなければならないという意識も芽生え、正義感が強まります。ただし、自我も育ってくるので利己的になりやすい一面もあります。とはいえ、基本的には子どもの判断に任せることが大切です。そのうえで、親としてどうしても見逃すことができない部分があれば、子どもの自尊心を傷つけない適切な方法で改善を促すように指導することが必要になります。
小学校高学年への接し方
難しい時期である小学校低学年の子どもには、どのような接し方をすればよいのでしょうか。この時期の子どもへの接し方は非常に重要です。接し方を間違うと、関係性が険悪になってしまう可能性もおおいにあります。よい関係を保ちながら子供と接するにはどのようにしたらいいのでしょうか。ここでは、小学校高学年の子どもへの接し方について説明します。
反抗期への対処
小学校高学年の子どもとうまく付き合うには、反抗期への正しい対処方法を理解しておくことが必要です。反抗期は自我の芽生えや体の変化により不安定な時期ともいえます。それまでは甘える対象であった親に対して、不安感やイライラ感が向くようになっていくでしょう。そのような変化を見ると大人のほうが深刻に考えてしまうことが多いです。とはいえ、反抗期は一時的なものなので、実際はそこまで気にする必要はありません。子どもの成長の証としてとらえてしまえばそれで十分です。子どものことに過度に干渉するのは避け、できるだけ遠くから見守るような意識をもつとよいでしょう。
小学校高学年への叱り方や注意の仕方
反抗期だと分かっていても、子どもの言動が度を過ぎている場合は叱ったり注意したりすることも必要です。その場合、どのような点に気を付けたらいいのでしょうか。反抗期の小学校高学年の子どもを叱るときは、言い方に注意するとよいです。たとえば、解決策を自分で考えさせるようにすると、親から干渉されているという雰囲気を抑えられます。また、命令口調にならないようにすることも大切です。子どものイライラにうまく付き合えるような対処法を考えましょう。
小学校高学年の心理の特徴は複雑

小学校高学年の子どもは、心身が成長の真っただ中にあります。そのため、状態は不安定にあるともいえます。ちょっとしたことでイライラしたり、不安になったりすることも少なくありません。そんな小学校高学年の子どもとうまく付き合うためには、心理状態の特徴を押さえてうまく付き合うことが大切です。とはいえ、反抗期になると子どもの変化に驚き、親も心配になることが多いです。しかし、だからといって子どもを無理に言い聞かせようとしたり、言動を強制させようとしたりするのは逆効果だといえるでしょう。そもそも小学校高学年にもなれば、子どもは自分の意思で物事を判断できるようになってきています。もちろん、誤った判断をすることもありますが、それをしっかり見守って陰から支えてあげることこそが親の役割だといえます。子どもが何をしても味方でいられるのは親しかいません。よって、小学校高学年の子どもに対しては特徴をとらえたうえでの接し方をし、様子を見守ってあげられるように大人も心に余裕をもつことを心掛けるべきです。
まとめ
小学校高学年の子どもたちは、心身ともに大きな変化を経験する時期です。身体的な成長や知的能力の発達に加え、自立心の芽生えや友人関係の変化など、様々な面で変化が訪れます。この時期の子どもたちの特徴を理解し、適切に対応することは、子どもの健全な成長を支える上で非常に重要です。
親としては、子どもの自立心を尊重しつつも、必要なときにはサポートを提供できる柔軟な姿勢が求められます。また、子どもとの対話を大切にし、信頼関係を築くことで、この変化の多い時期を共に乗り越えていくことができるでしょう。子どもの成長を見守り、寄り添いながら、親子でこの大切な時期を乗り越えていきましょう。
- 通信講座のSARAスクール編集部
-
心理カウンセラー資格やリンパケアセラピスト等の体系資格、食育資格などを扱うSARAスクール編集部が運営するコラムです。主に女性向けのキャリアアップやスキル習得を目的とした講座が多く、家事や育児と両立しながら学べる環境が整っています。資格取得を目的とした講座も充実しており、仕事や日常生活に活かすことが可能です。