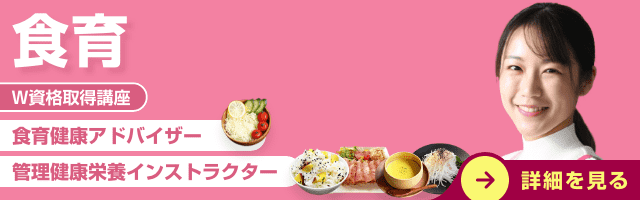マクロビオティックとは?手軽に始めるマクロビオティック料理
記事更新日:2024年8月30日健康と調和を重視するマクロビオティック料理は、自然のエネルギーを最大限に活用する食事法として、多くの人々に支持されています。
初心者でも手軽に始められるポイントやコツを押さえることで、日常の食生活に無理なく取り入れられます。
マクロビオティックとは、健康を目指した食事の考え方の1つです。自然を大事にする考えがベースとなっており、体に負担のない野菜や玄米を中心としたメニューに重きを置いています。最近では、マクロビオティック専門レストランなども増えており、多くの人の注目を集めています。食べ物の選び方にもこだわる必要がありますが、慣れてしまえばそこまで大変なものではありません。
今回は、「マクロビオティックって何?」という方のために、マクロビオティックの詳しい意味や考え方について説明します。

目次
マクロビオティックの概要と基本理念
マクロビオティックは、自然との調和を重視し、健康的な生活を実現するための食事法とライフスタイルの一環です。
これから紹介する内容では、マクロビオティックの基本理念、歴史的背景、そして具体的な実践方法について詳しく解説します。
食材の選び方や調理法において、自然の法則に従ったバランスを取ることが重要な要素です。
マクロビオティックを理解することで、より健康的で調和の取れた生活を送るための知識を深められるでしょう。
マクロビオティックとは
マクロビオティックは、健康と調和を重視した食事法であり、ライフスタイルの一環として多くの人々に取り入れられています。
ここでは、マクロビオティックの基本理念とその歴史的背景について詳しく解説します。
健康と調和を目指す食事法
マクロビオティックは、健康的な体と心を維持するための食事法として広く認知されています。
この食事法は、自然に近い形で食材を摂取することを推奨し、精製されていない玄米や新鮮な野菜、海藻、豆類などを中心に取り入れるものです。
これにより、ビタミンやミネラル、食物繊維を豊富に摂取でき、身体のバランスを保てます。
また、マクロビオティックは食事だけでなく、生活全般にわたる総合的な健康管理を目指しており、精神的な安定や調和も重視しています。
マクロビオティックの歴史と背景
マクロビオティックの起源は、日本の伝統的な食文化にあります。
この食事法は、桜沢如一(さくらざわ ゆきかず)によって体系化され、彼の著作や講演を通じて広まりました。
桜沢は、伝統的な日本の食文化を基に、西洋医学と東洋医学の知識を融合させた独自の理論を構築しました。
マクロビオティックは、食事を通じて体内の陰陽のバランスを整え、健康と長寿を達成することを目指しています。
桜沢の理論は、現在でも多くの人々に支持され、健康的なライフスタイルの一環として実践されています。
自然とのバランスを重視した食生活
マクロビオティックは、自然との調和を重視した食生活を提唱しています。
ここでは、その具体的な考え方と基本的な原則について解説します。
身土不二の考え方
身土不二とは、身体と土地が一体であるという考え方で、地元で育った食材をその土地の人々が食べることが健康に最も良いとされています。
これは、地元の食材がその地域の気候や環境に最適化されており、体がそれらの食材を最もよく吸収し、利用できるという理念に基づいています。
地元で取れる季節の食材を摂取することで、自然との調和が図れ、健康を維持することが可能です。
また、地元の農産物を選ぶことで、フードマイルの削減や地域経済の活性化にも貢献できます。
一物全体の原則
一物全体は、食材を丸ごと利用することを推奨する考え方です。
この原則は、食材の全体を使用することで、栄養素を余すことなく摂取し、自然のエネルギーを最大限に取り入れられるという理念に基づいています。
例えば、野菜の皮や根、葉を含めてすべて利用することが推奨されます。
これにより、食材の無駄を減らし、持続可能な食生活の実現が可能です。
また、食材を丸ごと利用することで、栄養バランスが良くなり、健康維持に役立ちます。
食材の陰陽理論
マクロビオティックの食事法では、陰陽理論が重要な役割を果たしています。
ここでは、陰陽の基本的な考え方と具体的な食材の分類について解説します。
陰陽の基本的な考え方
陰陽理論は、すべての物事を陰と陽の二つのエネルギーとして捉え、そのバランスを取ることが健康と調和をもたらすという考え方です。
陰は冷やす、柔らかい、湿っているという特性を持ち、陽は温める、硬い、乾燥しているという特性を持ちます。
このバランスを取ることで、体内のエネルギーが調和し、健康を維持できます。
マクロビオティックでは、食材や調理法、食べるタイミングなどすべてにおいてこの陰陽のバランスを考慮することが重要です。
食材の陰陽分類
食材の陰陽分類は、食材の性質や特性に基づいて行われます。
例えば、食材の育つ環境や形状、色、味などが陰陽の分類に影響を与えます。
一般的には、夏野菜や果物は陰性に分類され、体を冷やすのに効果的です。
一方、根菜や塩辛い食品は陽性に分類され、体を温める効果があります。
このように、陰陽のバランスを考慮した食材選びと調理法を実践することで、健康を維持し、調和の取れた食事を実現できます。
また、陰陽のバランスを考慮することで、季節や体調に応じた食事が可能となり、より効果的に健康を管理できます。
マクロビオティックの食事法は、単なる食事の選び方にとどまらず、生活全般にわたる総合的な健康管理が目的です。
自然との調和を重視し、食材の陰陽を考慮することで、体内のバランスを整え、健康を維持できます。
マクロビオティックの基本理念を理解し、実践することで、より健康的で調和の取れたライフスタイルを実現しましょう。
マクロビオティック料理の基本ルール
マクロビオティック料理は、健康と調和を追求するための食事法であり、その基本ルールは非常に重要です。
これから紹介する基本ルールを理解し、実践することで、心身の健康を維持し、自然との調和を図れます。
ここでは、食事の取り方、食材の選び方、そして避けるべき食材について詳しく解説します。
食事の取り方と基本ルール
マクロビオティックの食事法には、特定の取り方やマナーが存在し、これを守ることで食事の効果を最大限に引き出せます。
食事の順序とマナー
食事の順序とマナーは、マクロビオティックにおいて重要な要素です。
食事を摂る際には、まず副菜から始め、次に主食、最後に汁物という順序で食べることが推奨されます。
これにより、消化がスムーズになり、栄養素の吸収が効率的に行われます。
また、食事中のマナーも大切です。
感謝の気持ちを持って食材をいただくことが、心身の健康に良い影響を与えるとされています。
食事の前に「いただきます」と言い、食後に「ごちそうさまでした」と感謝の意を示すことが推奨されます。
噛むことの重要性
食べ物をよく噛むことは、マクロビオティックの基本ルールの一つです。
よく噛むことで、消化が促進され、栄養素の吸収が効率的に行われます。
また、噛むことで唾液が分泌され、消化酵素が活性化するため、消化器官の負担が軽減されます。
さらに、ゆっくりと食事をすることで、満腹感を得やすくなり、過食を防ぐ効果もあります。
一口ごとに30回以上噛むことを目指し、食事の時間を楽しむことが重要です。
食材の割合と選び方
マクロビオティックの食事では、食材の選び方とその割合が健康に大きな影響を与えます。
バランスの取れた食事を実現するための基本的なガイドラインは、以下の通りです。
主食と副食のバランス
主食と副食のバランスは、マクロビオティックの食事において非常に重要です。
主食としては、玄米や全粒穀物を中心に摂取し、副食としては、野菜、海藻、豆類、種実類をバランスよく取り入れることが推奨されます。
具体的には、全体の食事の50%以上を主食が占めるようにし、副食としては、30-40%を野菜、10-20%を豆類や海藻、種実類で構成することが理想的です。
このバランスを保つことで、必要な栄養素を効率的に摂取できます。
季節と地域に応じた食材選び
マクロビオティックでは、季節と地域に応じた食材選びが重要視されます。
地元で採れる旬の食材を選ぶことで、自然との調和を図るとともに、食材が持つ最適な栄養価を享受できます。
季節の変化に応じて食材を選び、例えば夏には冷やす効果のある野菜や果物を摂取し、冬には体を温める根菜類や温かいスープを取り入れることが推奨されます。
また、地域で採れる新鮮な食材を利用することで、地元の農業を支援し、環境への負荷を減らすことも可能です。
避けるべき食材とその理由
マクロビオティックの食事法では、特定の食材を避けることが健康維持に役立つとされています。
ここでは、避けるべき食材とその理由について詳しく解説します。
精製食品の影響
精製食品は、マクロビオティックにおいて避けるべき食材の一つとされています。
白米や白パン、精製された砂糖などの精製食品は、栄養素が失われており、血糖値の急激な上昇を引き起こす可能性が高いです。
精製食品を摂取することで、エネルギーの供給は得られるものの、ビタミンやミネラル、食物繊維が不足し、長期的には栄養バランスの崩れを招くことがあります。
そのため、玄米や全粒粉パン、自然の甘味料を使用することが推奨されます。
添加物や化学調味料のリスク
添加物や化学調味料は、健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、マクロビオティックの食事法では避けるべきとされています。
これらの化学物質は、加工食品に多く含まれており、摂取することでアレルギー反応や消化不良を引き起こすことがあります。
また、長期的に添加物や化学調味料を摂取することで、体内に有害物質が蓄積し、免疫力の低下や慢性疾患のリスクが増加する可能性が高いです。
マクロビオティックでは、自然の調味料や無添加の食品を選ぶことで、健康を維持し、体内のバランスを整えることが重視されます。
マクロビオティック料理の基本ルールを理解し、実践することで、心身の健康を維持し、自然との調和を図れます。
食事の取り方や食材の選び方を見直し、健康的な食生活を送るための第一歩を踏み出しましょう。
マクロビオティック料理を始めるためのステップ
マクロビオティック料理は、健康と調和を重視するライフスタイルを支える食事法です。
初心者でも簡単に始められるステップを踏むことで、日常生活に自然に取り入れられます。
ここでは、マクロビオティック料理を始めるための具体的なステップを紹介します。
初心者でも簡単に始められるコツ
マクロビオティック料理を始める際には、無理なく続けられるようにするための基本的なコツがあります。
ここでは、必要な調理器具や基本的な準備、毎日の食事に取り入れる方法について詳しく解説します。
必要な調理器具と基本的な準備
マクロビオティック料理を始めるためには、いくつかの基本的な調理器具と準備が必要です。まず、玄米を炊くための炊飯器や圧力鍋があると便利です。
また、野菜を蒸すための蒸し器や、だしを取るための鍋も必要です。
これらの器具は、マクロビオティック料理を効率よく進めるための基本的なツールとなります。
準備としては、まず台所を整理し、必要な調理器具を揃えます。
次に、マクロビオティックに適した食材を購入しましょう。
玄米、全粒穀物、豆類、海藻、季節の野菜などが基本となります。
これらの食材は、自然食品店やスーパーで手に入れられます。
毎日の食事に取り入れる方法
毎日の食事にマクロビオティックを取り入れるためには、無理のない範囲で少しずつ始めることがポイントです。
まずは、朝食に玄米のおにぎりや味噌汁を取り入れてみましょう。
また、昼食には玄米ご飯と野菜の煮物、夕食には玄米ご飯と豆腐のステーキなどを取り入れることで、バランスの取れた食事を実現できます。
食材選びにおいても、地元で採れた旬の食材を選ぶことが大切です。
これにより、栄養価が高く、新鮮な食材を摂取でき、自然との調和を図れます。
また、調理法においても、シンプルな調理を心がけることで、食材本来の味を楽しめます。
玄米の炊き方とポイント
玄米はマクロビオティックの食事の基本です。
美味しく炊くためには、適切な選び方と保存方法、そして炊き方のポイントを押さえることが重要です。
玄米の選び方と保存方法
良質な玄米を選ぶためには、粒が揃っており、色が均一なものを選びましょう。
また、玄米は鮮度が大切ですので、できるだけ新しいものを選ぶことが推奨されます。
購入した玄米は、湿気を避け、風通しの良い冷暗所で保存します。
密閉容器に入れ、冷蔵庫で保存することも一つの方法です。
美味しく炊くためのコツ
玄米を美味しく炊くためには、以下の手順を守ることが大切です。
1. まず、玄米をよく洗います。数回水を替えながら丁寧に洗い、余分なぬかを落とします。
2. 次に、洗った玄米を水に浸けます。
浸水時間は最低でも4時間、理想的には一晩浸けることが推奨されます。
これにより、玄米が柔らかくなり、消化がしやすくなるのです。
3. 炊く際には、炊飯器や圧力鍋を使用します。
圧力鍋を使う場合、玄米と水の比率は1:1.5から1.75が目安です。
炊飯器の場合は、取扱説明書に従ってください。
4. 炊き上がったら、15分ほど蒸らすことで、より美味しく仕上がります。
マクロビオティックのだしの取り方
だしは、マクロビオティック料理において重要な役割を果たします。
だしを使うことで、料理の風味が豊かになり、栄養価も向上します。
ここでは、昆布だしと椎茸だしの取り方について解説します。
昆布だしの基本
昆布だしは、マクロビオティック料理の基本のだしです。
昆布を使っただしは、旨味が豊かで、様々な料理に使えます。
1. まず、昆布を軽く拭き、水に昆布を浸け一晩冷蔵庫で浸け置きます。
2. 翌日、昆布を取り出し、浸け置いた水を火にかけてください。
3. 沸騰直前で火を止め、昆布を取り出せば昆布だしの完成です。
昆布だしは、味噌汁や煮物、炒め物に使用できます。
椎茸だしの作り方
椎茸だしも、マクロビオティック料理でよく使われるだしの一つです。
干し椎茸を使うことで、深い旨味と香りが得られます。
1. 干し椎茸を水に浸け、一晩冷蔵庫で浸け置きます。
2. 翌日、椎茸を取り出し、浸け置いた水を火にかけてください。
3. 沸騰直前で火を止め、椎茸を取り出します。
椎茸だしは、スープや煮物、鍋料理などに使用できます。
また、だしを取った後の椎茸は、細かく切って料理に加えると、一層風味が増します。
簡単にできるマクロビオティック料理レシピ
マクロビオティック料理は、健康的でバランスの取れた食事を楽しむための優れた方法です。
ここでは、初心者でも簡単に作れる美味しいメインのおかずとヘルシーな副菜・汁物のレシピを紹介します。
美味しいメインのおかず
メインのおかずは、満足感を得られるようなボリュームと栄養価を兼ね備えた料理が理想です。
ここでは、玄米と野菜の炒め物、そして豆腐ステーキの作り方を紹介します。
玄米と野菜の炒め物
玄米と野菜の炒め物は、簡単に作れて栄養満点の一品です。
玄米のプチプチとした食感と、野菜のシャキシャキ感が絶妙にマッチします。
【材料】
● 玄米ご飯:2カップ
● 玉ねぎ:1個
● ピーマン:1個
● にんじん:1本
● ブロッコリー:1/2株
● ごま油:大さじ1
● 醤油:大さじ2
● みりん:大さじ1
● 塩:少々
● こしょう:少々
【作り方】
1. まず、玉ねぎ、ピーマン、にんじん、ブロッコリーを一口大に切ります。
2. フライパンにごま油を熱し、中火で玉ねぎを炒めます。
玉ねぎが透明になったら、他の野菜を加えてさらに炒めます。
3. 野菜がしんなりしてきたら、玄米ご飯を加えて炒め合わせます。
4. 醤油とみりん、塩、こしょうを加え、全体に味が馴染むように炒めます。
5. すべての材料がしっかりと混ざり合ったら、火を止めて器に盛り付けます。
豆腐ステーキの作り方
豆腐ステーキは、外はカリッと、中はふんわりとした食感が楽しめる一品です。
たれを絡めることで、さらに美味しさが増します。
【材料】
● 木綿豆腐:1丁
● 片栗粉:適量
● ごま油:大さじ2
● 醤油:大さじ2
● みりん:大さじ1
● 砂糖:小さじ1
● おろし生姜:小さじ1
【作り方】
1. 木綿豆腐は水切りしておきます。
キッチンペーパーで包み、重しを乗せて15分ほど置きます。
2. 水切りした豆腐を厚さ1cm程度にスライスし、片栗粉をまぶします。
3. フライパンにごま油を熱し、中火で豆腐を焼きます。
両面がきつね色になるまでしっかりと焼きます。
4. 別のボウルに、醤油、みりん、砂糖、おろし生姜を混ぜ合わせてたれを作ります。
5. 焼き上がった豆腐にたれを絡め、全体に味が馴染むように軽く炒めます。
6. たれが豆腐にしっかりと絡まったら、器に盛り付けます。
ヘルシーな副菜と汁物
マクロビオティック料理では、副菜と汁物も重要な役割を果たします。
ここでは、季節の野菜を使った副菜と、簡単に作れる味噌汁のレシピを紹介します。
季節の野菜を使った副菜
季節の野菜を使った副菜は、新鮮で栄養価が高く、食卓に彩りを添えます。
ここでは、シンプルで美味しい一品を紹介します。
【材料】
● ほうれん草:1束
● にんじん:1本
● しめじ:1パック
● ごま油:大さじ1
● 醤油:小さじ1
● みりん:小さじ1
● 白ごま:適量
【作り方】
1. ほうれん草はさっと茹でて、水気を切り、一口大に切ります。
2. にんじんは細切りにし、しめじは石づきを取ってほぐします。
3. フライパンにごま油を熱し、中火でにんじんとしめじを炒めます。
野菜がしんなりしてきたら、ほうれん草を加えます。
4. 醤油とみりんを加え、全体に味が馴染むように炒めます。
5. 最後に白ごまをふりかけ、器に盛り付けます。
簡単に作れる味噌汁
味噌汁は、マクロビオティック料理において欠かせない一品です。
シンプルな具材で作ることで、素材の風味を活かした味わいを楽しめます。
【材料】
● 水:4カップ
● 昆布:10cm
● かつお節:30g
● 味噌:大さじ2
● 豆腐:1/2丁
● わかめ:10g
● ねぎ:適量
【作り方】
1. 水に昆布を入れ、火にかけます。
沸騰直前で昆布を取り出し、かつお節を加えて火を止めます。
数分置いてから、こし器でこします。
2. だしが取れたら再び火にかけ、豆腐を一口大に切って加えます。
わかめも加えてさっと煮ます。
3. 味噌を溶き入れ、沸騰させないように気をつけながら全体に味が馴染むようにします。
4. 最後に刻んだねぎを加え、器に盛り付けます。
マクロビオティック料理は、シンプルながらも豊かな風味と栄養が楽しめる食事法です。
これらのレシピを日常生活に取り入れることで、健康的でバランスの取れた食事を実現できます。
マクロビオティックとは

マクロビオティックと、どういったものでしょうか。以外に感じる方もいるかもしれませんが、実はマクロビオティックのルーツは、日本にあります。まずは、基礎的な知識について説明します。
さまざまな呼び方
マクロビオティックは、ほかにもいろいろな呼び方があります。「マクロビ」や「マクロ」と略されることも多いです。また、日本では、マクロビオティックのことを「正食」と呼んでいたため、いまでもそういった呼び方をすることもあります。また、マクロビの考え方を反映した呼び方として、「玄米菜食」という言い方をすることもあるので覚えておきましょう。
マクロビオティックのはじまり
マクロビオティックは、その名称から海外で生まれたものだと思っている人も多いです。しかし、マクロビオティックは、実は日本で生まれた考え方です。マクロビオティックを確立させたのは、桜沢如一という人物だといわれています。桜沢は、明治に石塚左玄が考案した食事方法に陰陽の考え方を取り入れることで、正食を生み出しました。その後、正食は海外で広まったのですが、その際にマクロビオティックという名称で紹介されていました。日本でマクロビオティックが広く知られるようになったのは、この後のことです。そのため、日本名の正食よりも欧米向けの名称である、マクロビオティックという呼び方のほうがより世間に浸透しています。
語源
マクロビオティックということばの語源を知るためには、まずこのことばを3つに区切る必要があります。まず、「マクロ」は大きいや長いという意味があります。「ビオ」は生命です。そして、「ティック」は術や学という意味になります。これらを合わせた「マクロ・ビオ・ティック」には、「生命を大きくし、長く保つための方法」という意味があるといえます。
ベジタリアンとは別物!
マクロビオティックでは、野菜を中心とした食生活が大切にされています。そのため、マクロビオティックとベジタリアンとの違いが分からないという人も多いです。両者の一番の違いは、そういった食生活に取り組む背景であるといえるでしょう。ベジタリアンが野菜中心の食事をしているのは、主に宗教や思想が大きな理由となっています。それに対してマクロビオティックは、自分と食べ物の関係を読み解くことで健康を目指す、という観点から野菜に特化した食事をとることが推奨されています。
マクロビオティックの基本
マクロビオティックでは、とても重視されている原則や考え方があります。これらを理解することで、マクロビオティックを深く知ることができるはずです。また、これらの原則や考え方を意識すれば、よりマクロビオティックの実践がしやすくなるでしょう。
マクロビオティックの2大原則
マクロビオティックには重要な原則が2つあり、「2大原則」として大切にされています。1つ目の原則は、「身土不二」です。これは、「しんどふじ」と読みます。身土不二とは、人間の体は生まれ育った土地と一体になっているということを示しています。そのため、マクロビオティックでは、生まれ育った場所でとれた作物を食べることを推奨しています。マクロビオティックでは、それがいちばん体に適した食材だと考えられているのです。 2つ目の原則は、「一物全体」です。これは、「いちぶつぜんたい」と読みます。一物全体とは、ものはまるごと1つで全てだと考えるという意味です。そのため、マクロビオティックでは、自然の恵を残さず丸ごと食べることが大切だと考えられています。普段なら捨ててしまうことも多い部分も、マクロビオティックではなるべく全て食べるようにします。野菜の皮、種、根などは、きれいに洗えば立派な食材として食べることが可能です。
マクロビオティックで重要な「陰陽論」
マクロビオティックでは、「陰陽論」という考え方も重要です。マクロビオティックでは、全ての食べ物に「陰」と「陽」があると考えます。陰性は、遠心力を示すとともに、静かさや冷たさなどを表しています。また、陽性は、求心力を示すとともに、動きや熱さなどを表すとされています。マクロビオティックでは、これらのバランスがとれた状態を「陰陽調和」として大切にしています。 陰性の食材は、育つときに上に向かって伸び、体を冷やす作用があるといわれています。たとえば、夏にとれるキュウリです。また、陽性の食材は、育つときに地中に向かって伸び、体を温める作用があると考えられています。たとえば、冬にとれるゴボウなどです。マクロビオティックでは、これらの食材をバランスよく摂取することで、健康な体を保つことができるとされています。
マクロビアンとベジタリアンの違い
マクロビオティックの基本は、玄米と野菜を中心にした食事です。そのため、「ベジタリアンと同じでは?」と感じる人もいるでしょう。しかし、これらには、決定的な違いが存在しています。違いをしっかり理解することで、マクロビオティックへの理解を深めましょう。
ベジタリアン
ベジタリアンは、宗教や思想に基づき、野菜を基本とした食生活を送る人のことです。ベジタリアンの中にもさまざまな分類があります。そのため、ベジタリアンでも動物系のタンパク質を摂取する人もいます。また、宗教上の理由から、特定の動物の肉のみを避ける人もいるようです。肉や魚を少しは食べるという人であっても、週に一度など少ない頻度におさえていることが多いです。ベジタリアンは、宗教や思想により厳格に食べられる食品を分けている人が多いのが特徴だといえます。
マクロビアン
マクロビオティックの考え方に基づいた食生活を送るマクロビアンは、特定の宗教や思想をもっているということは条件になりません。その人の宗教や思想の考え方と矛盾しないということが条件になりますが、どのような思想や宗教をもっている人でも実践することは可能です。 マクロビオティックで重要なのは、すでに説明した身土不二と一物全体、そして陰陽論です。これらに基づいて、玄米菜食を基本としています。マクロビオティックでは、食べてはいけないものが定められているわけではありません。そのため、肉や魚を食べても大丈夫です。しかし、これらは体に負担がかかりやすいという意味であまり食べないほうがよいとされています。
マクロビオティックの意味を理解して食事から健康に

マクロビオティックは、体を健康に保つ方法として、毎日の食生活を改善することを提唱しています。マクロビオティックの考え方に基づいて食事をしていけば、体力が強化されたり、冷え性といった体の悩みが解消されたりするなどの効果が得られます。また、体の健康だけでなく、精神的にも安定しやすくなるといわれており、メリットが豊富です。ストレスにも強くなるので、毎日の生活がより楽しく感じられるようになるでしょう。
マクロビオティックは、ベジタリアンなどの考え方と似ていますが、それぞれの背景はまったく異なっています。健康を第一に考える食生活を目指すなら、マクロビオティックがいちばん適しているといえるでしょう。初めから玄米と野菜だけを食べようとする必要はありません。少しずつマクロビオティックの食事のしかたに慣れる期間を設けることも大切です。マクロビオティックの食事を取り入れることで、食べ物から健康を保ちましょう。
マクロビオティックの考え方
次に、マクロビオティックの具体的な考え方についてみていきましょう。マクロビオティックには、2つの考え方があります。
2大原則
マクロビオティックには、2大原則があります。1つ目は、「身土不二(しんどふじ)」です。これは、体と土地は一体であるという考え方です。具体的には、自分自身の体は生まれ育った環境と切り離して考えることはできず、その土地で採れた食べ物を食べるのがもっとも体に合っているということを示しています。 2つ目は、「一物全体(いちぶつぜんたい)」です。これは、どんなものでも丸ごと1つを食べるのが重要だという意味を示しています。たとえば、ある植物を食べるときは、なるべくその皮や葉、種などの全てを食べるべきだとされています。そのため、マクロビオティックでは、食材を余すことなく全て使用するのが基本です。
マクロビオティックの「陰陽論」
マクロビオティックには、陰陽論の考え方が含まれています。そのため、マクロビオティックでは、それぞれの食べ物には「陰」または「陽」の要素があり、そのバランスを整えるのが重要だとされています。陰陽のバランスを保つ食事を継続することができれば、健康によい効果を得ることが可能です。マクロビオティックを実践するなら、まずは食べ物の陰陽を知り、バランスのとれた食事を心掛けることから始めるべきでしょう。
マクロビオティック食のメリット
マクロビオティックの食事をとることには、さまざまなメリットがあります。たとえば、次のようなメリットです。
身体的メリット
マクロビオティック食を継続的に食べていれば、体力を強化し、健康的な体を維持することができます。また、美肌やダイエットなどの美容効果も高いです。冷え性や不眠症など、体の悩みを解消することにもつながります。また、生活習慣病を予防したり、老化を和らげたりするなどの作用も期待できます。
精神的メリット
マクロビオティック流の食事を続けていると、ストレスを感じることが少なくなり、気持ちが明るくなります。精神力も強くなるので、エネルギッシュになることが多いです。人との関係も円滑になり、運がよくなるでしょう。また、頭がすっきりさえるので、問題に対処する力も高めることができます。
社会的メリット
マクロビオティックの考え方を食事に取り入れると、地産地消を推進することになるので、地域の産業を支援することにつながります。身近なところで手に入るものを中心に食べることで、運送時の排気ガスによる環境汚染を減らすといったエコロジー効果も期待できます。
マクロビオティック食の取り入れ方
マクロビオティックは、健康に対してだけでなく、さまざまなよい効果をもたらします。最後に具体的な食事に関する考え方をみてみましょう。
食材バランスのガイドライン
マクロビオティックでは、食事のバランスの目安が決められています。まず、未精製の全粒穀物は50~60%摂取するのが重要です。未精製の全粒穀物とは、主に玄米のことをさしています。また、野菜が25~30%、豆や海藻は10~15%がよいとされています。ほかには、ナッツや果物を5~10%取るようにするとよいでしょう。
基本は玄米食
マクロビオティックでは、主食は玄米とするのが基本です。玄米の陰陽バランスは中庸なので、マクロビオティック的にはとてもよい食品とされています。玄米にはビタミンやミネラル、食物繊維といった栄養素が非常に豊富に含まれています。そのため、白米を食べるよりも、健康効果の高い食事を実現することが可能です。
野菜はまるごと
一物全体の考えに基づき、野菜を食べるときは皮も含めて丸ごと食べるようにします。そのため、安全で新鮮な食材を入手することが大切です。信頼できる売り場で、有機栽培や無農薬栽培の野菜を選ぶようにしましょう。
調味料・甘味料
マクロビオティック食を作るときは、調味料や甘味料にもこだわる必要があります。未精製のものを選び、化学調味料が入っているものは避けるようにしてください。
避けるべき食材
マクロビオティックでは、食べてはいけないものはありません。ただし、肉や卵、白砂糖、化学調味料といった食品は、なるべく避けたほうがよいという考え方があります。その理由は、こういった食品は体に負担がかかりやすいからです。どうしても食べたいときは、食べても問題はありません。とはいえ、食べ過ぎにならないように気を付けましょう。
食べ方
マクロビオティック食は、よく噛みながらゆっくり食べることが大切です。食材本来の味を楽しみながら、食事をしましょう。食べ過ぎは禁物なので、満腹になり過ぎないよう必要な量だけをとることを心掛けてください。
マクロビオティックとは健康重視の玄米菜食のこと

マクロビオティック食を食べていると、心と体によい影響をたくさん感じることができます。基本は玄米や野菜を中心とすべきですが、とくに最初のうちは無理のない範囲で少しずつ取り入れていけばOKです。マクロビオティックの考え方で、自然と健康的な食生活を送れるようになりましょう。
まとめ
マクロビオティック料理は、健康と調和を追求するための食事法で、初心者でも無理なく始められる方法がたくさんあります。
基本的な調理器具を揃え、玄米や季節の野菜を取り入れることで、日常の食生活に自然とマクロビオティックを取り入れられます。
玄米の炊き方やだしの取り方などの具体的なテクニックを学ぶことで、シンプルで栄養豊富な料理を楽しめるでしょう。
また、手軽に作れるレシピを実践することで、マクロビオティックの魅力を存分に味わいながら、健康的なライフスタイルを実現する第一歩を踏み出せます。
- 通信講座のSARAスクール編集部
-
心理カウンセラー資格やリンパケアセラピスト等の体系資格、食育資格などを扱うSARAスクール編集部が運営するコラムです。主に女性向けのキャリアアップやスキル習得を目的とした講座が多く、家事や育児と両立しながら学べる環境が整っています。資格取得を目的とした講座も充実しており、仕事や日常生活に活かすことが可能です。