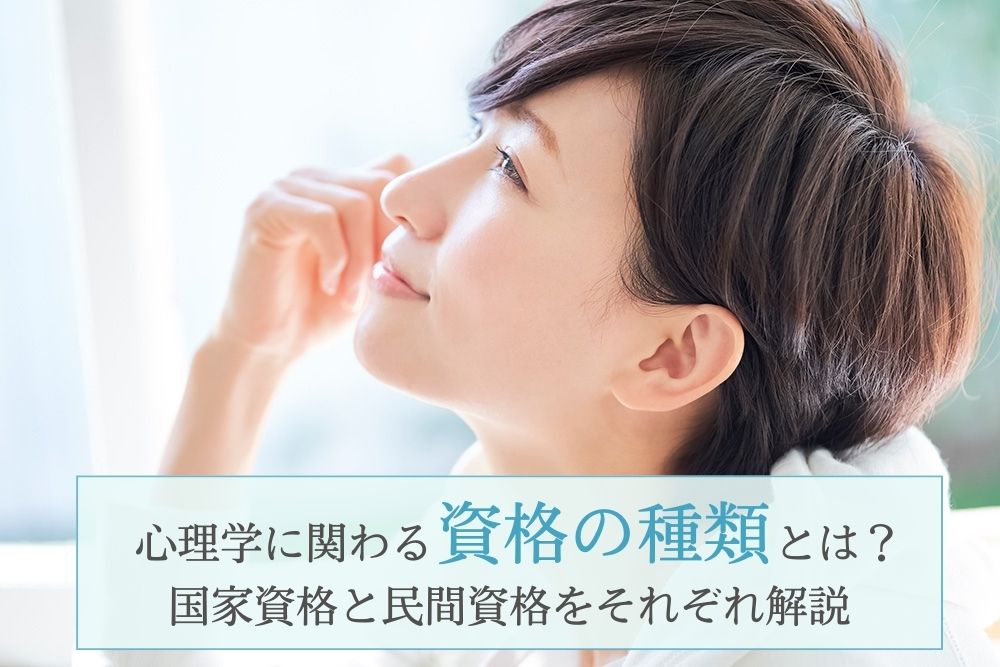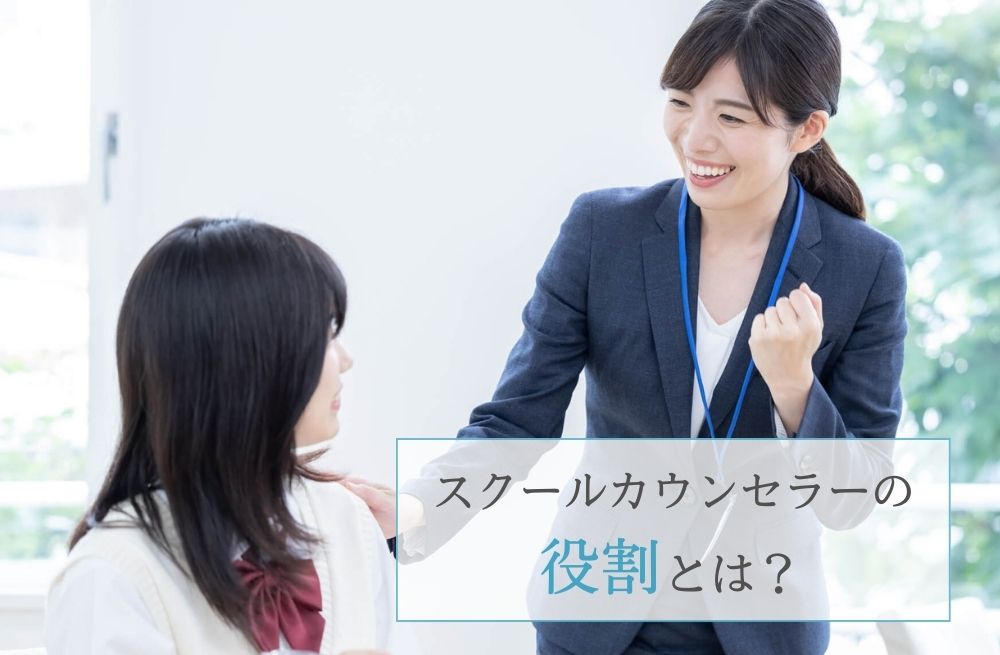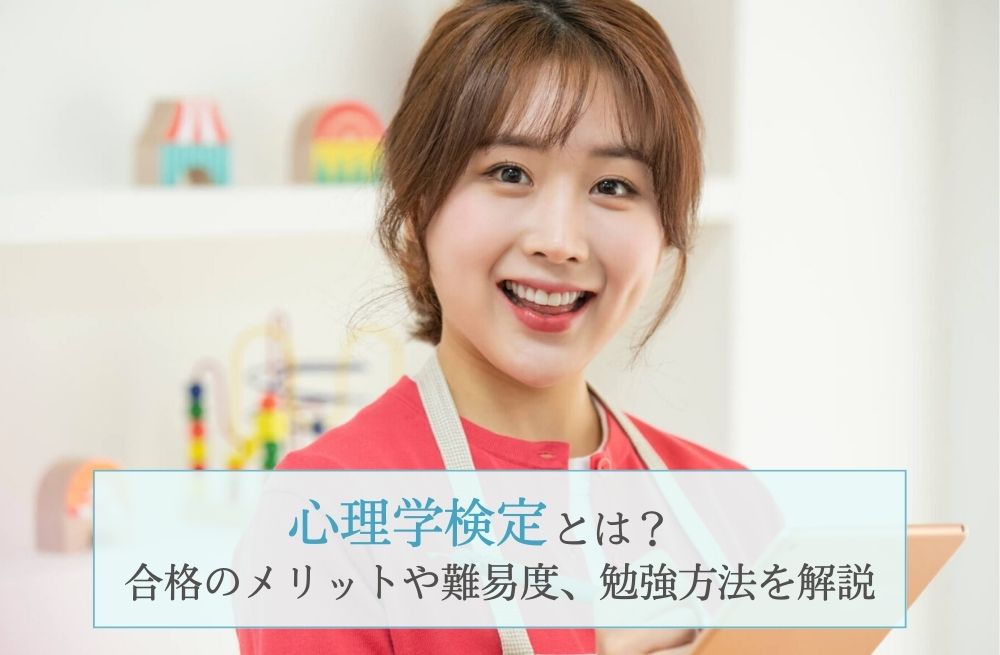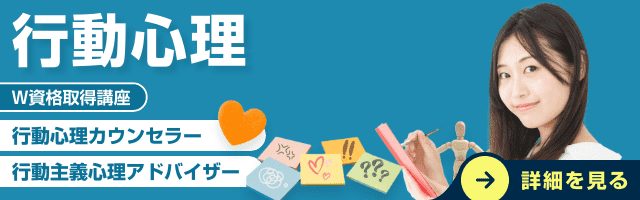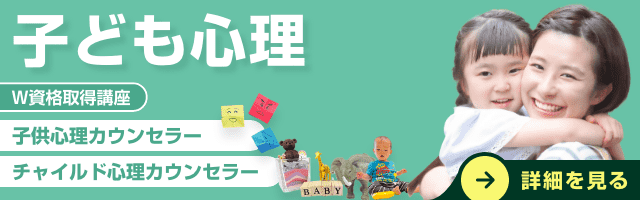心理カウンセラーになるには?必要な資格や活躍の場について解説!
記事更新日:2025年9月16日現代社会ではストレスや人間関係の悩みを抱える人が増加し、心理カウンセラーの需要は年々高まっています。やりがいのある仕事だからこそ、「心理カウンセラーになりたい!」「心理カウンセラーの資格を取りたい!」と考える人も増えました。
本記事では、心理カウンセラーになる方法を解説します。心理カウンセラーになるために必要な資格や学歴、具体的なキャリアパスまで幅広く解説しているのでご参考ください。

目次
目次
心理カウンセラーとはどんな仕事?

心理カウンセラーとは、心に悩みや不安を抱える人の話を聴き、心の整理や回復をサポートする専門職です。医師のように診断・投薬・治療をするのではなく、対話を通して相談者自身が問題に気づき、乗り越える力を育てます。
心理カウンセラーの主な仕事内容
相談者の話を丁寧に聴き、気持ちの整理や問題解決のサポートを行います。
・ 心理検査・アセスメント
必要に応じて性格検査やストレスチェックなどを行い、心の状態を把握します。
・ 記録・報告書の作成
面談内容を記録し、他機関と連携が必要な場合は報告書を作成します。
・ 他機関との連携・紹介
医療機関や福祉サービスなど、支援先を紹介します。
・ 心理教育・研修の実施
学校や企業で、ストレス対処法などの講義や研修を行います。
また、心理カウンセラーの仕事は、ただ話を聞くだけではありません。必要に応じて認知行動療法や来談者中心療法などの専門技法を用いることもあります。相談者の心に寄り添いながら解決に向けた一歩を後押しする、やりがいのある仕事として確立しています。
心理カウンセラーの主な就職先

心理カウンセラーは、医療・教育・福祉・企業などさまざまな分野で活躍しています。ここでは、心理カウンセラーの主な就職先ごとに特徴を紹介します。
学校・教育機関
学校・教育機関で働く心理カウンセラーは、生徒だけでなく保護者や教職員も対象に「学校全体の心のサポート役」として活動します。
【特徴】
・ 生徒の不登校、いじめ、発達の悩みなどに対応する
・ 保護者や教職員からの相談にも応じる
・ 面接時間が限られることが多く、短時間での対応力が求められる
・ 教育委員会などの公的機関に所属し、複数校を巡回するケースもある
学校・教育機関で働く心理カウンセラーには、子どもたちの変化に早く気づき、限られた時間の中で的確な支援を行うスキルが求められます。また、保護者や教職員からの相談に応じたり、外部の専門機関と連携したりすることも多いです。
一般企業
一般企業で働く心理カウンセラーは、産業カウンセラーとして社員のメンタルヘルスを支える役割を担うことが多いです。
【特徴】
・ 社員のストレスやメンタル不調に関する相談対応が中心
・ 産業医や人事部門との連携による職場改善のサポートをする
・ メンタルヘルス研修やストレス対処法などの講師役も担う
・ ハラスメントや職場の人間関係に関する相談が多い
「働きやすい職場づくり」や「組織の生産性向上」に貢献することが目的で、個別相談だけでなく、社内研修や職場環境の改善提案など企業全体を視野に入れた活動が求められます。
また、プライバシーへの配慮と組織としての対応の両立が必要なため、高い倫理性と実務的な判断力も欠かせません。社員の「こころの安全基地」として信頼される存在であることを目指します。
福祉施設・医療機関
福祉施設・医療機関で働く心理カウンセラーは、医療的・福祉的な支援が必要な人々と向き合い、より専門的かつ継続的な心理支援を行います。
【特徴】
・ 精神疾患や発達障害をもつ方への心理的支援を行う
・ 医師・看護師・ソーシャルワーカーなど多職種と連携する
・ カウンセリングだけでなく、生活支援や家族支援も行う
・ 長期的な支援が必要なケースが多く、信頼関係の構築が重要
特徴として、心のケアだけでなく家族や医療スタッフとの連携を通じた「生活全体の質の向上」に関わることが多いことが挙げられます。
心理検査やアセスメント(評価)を担う場面も多く、専門知識が求められることも。チーム医療や多職種協働の現場で働くことになるため、スタッフ間における信頼関係の構築が欠かせません。
行政機関
行政機関で働く心理カウンセラーは、地域に根ざした公的支援の一環として、子どもから高齢者まで幅広い層の心理的課題に対応します。
【特徴】
・ 市区町村の相談窓口(福祉・子育て・教育など)での心理相談を担当
・ DV・虐待・生活困窮など複雑なケースに関わることもある
・ 地域住民への心理教育や啓発活動を行うこともある
・ 相談記録や報告書などの事務処理が多い
虐待・DV・ひきこもり・生活困窮など複雑かつ深刻なケースを扱うことも多く、臨床的な知識と高い判断力が求められます。また、学校・医療機関・福祉施設・警察などと連携し、地域全体で問題解決に向けて動く「ハブ」のような役割も担うのが特徴です。
市民生活のセーフティーネットとしての役割も求められるため、幅広い案件に対応できる柔軟さが必要です。
独立・開業
独立・開業して働く心理カウンセラーになると、自分のペースで相談業務ができる自由度が高まります。その分、集客・契約・納税など運営に欠かせない事務手続きも多くなるのがポイントです。
【特徴】
・ 自身でカウンセリングルームや心理相談所を開設する
・ 個人のニーズに合わせた自由なカウンセリングが可能
・ 予約管理や集客、経営面のスキルも求められる
・ 専門分野(子ども・夫婦関係・職場のストレスなど)に特化するケースも多い
相談者との信頼関係を築くことはもちろん、安定した集客やサービスの質を維持する視点も欠かせません。心理カウンセラーとしての実力と経営を安定させる力の両方を磨くことが、成功のカギとなります。
オンラインカウンセリングの普及が進んでいる昨今、地域に縛られずに活動できる機会も増えているのが特徴です。
心理カウンセラーの給料・年収は?

心理カウンセラーの給与は、勤務先や保有資格、経験によって異なりますが、令和5年度の平均年収は約459万円(※1)となっています。
資格別の年収
心理カウンセラーの資格別に年収を見てみると、唯一の国家資格である公認心理師をはじめ、民間資格の臨床心理士や産業カウンセラーなど、主要な資格保有者の平均年収は概ね300万〜400万円前後であり、資格による収入の差はそれほど大きくないことがわかります。
| 資格 | 平均年収 |
|---|---|
| 公認心理師 | 300万円~400万円(※2) |
| 臨床心理士 | 300万円~400万円 |
| 産業カウンセラー | 300万円~400万円 |
| 社会福祉士 | 350万円~400万円 |
| 精神保健福祉士 | 300万円~500万円 |
勤務先別の年収
勤務先別に心理カウンセラーの年収データを紹介します。平均年収(参考値)は、学校が約220万円〜560万円、企業が約300万円〜400万円、医療機関が約400万円とばらつきが見られます。
| 勤務先 | 平均年収 |
|---|---|
| 学校 | 220万円〜560万円 |
| 企業 | 300万円〜400万円 |
| 医療機関(病院・クリニック) | 約400万円 |
スクールカウンセラーは非常勤での雇用が一般的である一方、医療機関のカウンセラーは、常勤で1ヵ所に勤務する場合もあれば、非常勤として複数の施設を掛け持ちすることもあります。
また企業カウンセラーは、勤務先企業の給与体系に基づいて固定給となることが多く、これらの年収は就業形態によって左右されます。
収入を重視する場合は、勤務先の待遇や雇用形態に注目することが大切です。
※1 参考:厚生労働省 職業情報提供サイト(日本版O-NET)|カウンセラー(医療福祉分野)
※2 参考:公認心理師の活動状況等に関する調査(一般社団法人 日本公認心理師協会)
心理カウンセラーになるには?

心理カウンセラーになるには、状況や目的に応じていくつかのルートがあります。以下で代表的なものについて紹介します。
大学・大学院で学ぶ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学習期間 | 約4年~6年(大学4年+大学院2年など) |
| 費用 | 大学・大学院合わせて数百万円規模 |
| メリット | ・基礎から専門知識がしっかり学べる ・実習や研究で実践力が身につく ・資格取得に有利になることが多い |
| デメリット | ・時間がかかる ・学費や生活費の負担が大きい ・学業・実習・資格勉強の両立が難しい |
大学・大学院の場合、基礎から専門的な知識まで幅広く習得できるため、実践力や理論をしっかりと身につけられます。また、実習や研究を通じて現場での対応力も養うことができ、臨床心理士や公認心理師などの専門資格取得にも有利に働きます。
一方、学習期間が長く、学費や生活費などの経済的負担も大きくなることがデメリットです。心理カウンセラーになることだけを集中的に学ぶわけではないため、最短距離での目指し方ではない点に注意しましょう。
専門学校・短大で学ぶ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学習期間 | 専門学校:2〜3年、短大:2年 |
| 費用 | 大学よりも比較的安価なことが多い |
| メリット | ・実践的なスキルを短期間で学べる ・費用や時間の負担が軽い ・就職支援が手厚い |
| デメリット | ・専門知識の幅が狭くなる ・資格取得の選択肢が限られる ・学問的な理論学習が浅くなる可能性がある |
専門学校や短大は、より実践的なスキルを短期間で身につけやすいことが魅力です。大学や大学院に比べて学費や学習期間の負担が軽いため、経済的・時間的な制約がある方に適しています。また、就職支援が充実している学校も多く、早期に現場で働き始めたい人にとっては有利な選択肢といえます。
一方、学べる内容は実践重視である点に注意しましょう。専門的な理論学習や研究をしたいときは、大学・大学院の方がおすすめです。
通信教育で学ぶ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学習期間 | 自分のペースで進められるため個人差あり |
| 費用 | 通学に比べて比較的安価 |
| メリット | ・場所や時間を選ばず学べる ・仕事や家庭と両立しやすい ・自分のペースで進められる |
| デメリット | ・実習や対面指導が少なく実践経験が不足しがち ・モチベーションの維持が難しい場合がある ・質問や相談のタイムラグが生じやすい |
通信教育は、仕事や育児などで忙しい方でも自宅や好きな場所で学習を進められる柔軟性が大きな魅力です。社会人になってから通信教育を利用したり、大学や専門学校と並行して学んだりすることもでき、自分のやる気次第でいつからでも始められるのもポイント。高校生や高卒生でも利用できます。費用負担も少なく、経済的な負担を軽減しながら心理学の基礎を学びたい人に適しています。
一方、スクールによってはモチベーションの維持や質問への即時対応が難しいことがあるので注意しましょう。サポートが手厚いスクールや質問対応が充実しているスクールを選ぶと、通信教育のデメリットを大幅に改善できます。
独学
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学習期間 | 自分のペースで自由に設定できる |
| 費用 | 教材費や書籍代のみで比較的低コスト |
| メリット | ・費用を抑えて学べる ・時間や場所を自由に使える ・自分の興味に合わせて学習できる |
| デメリット | ・専門的な指導やフィードバックが得にくい ・実践経験を積む機会が少ない ・モチベーション維持が難しい場合がある |
独学で資格を取るなど工夫し、心理カウンセラーになることも可能です。独学は、費用を大幅に抑えつつ自分のペースで自由に学べる点が魅力です。教材や書籍も自由に選べて、自分の興味や理解度に合わせて柔軟に学習計画を立てられるため、時間や場所の制約がある方に適しています。
ただし、専門的な知識の習得やスキルの向上には限界があり、疑問点の解消や正確な理解には専門家の指導やフィードバックが欠かせない点に注意が必要です。資格取得だけを目的にするのであれば独学も選択肢に入りますが、実務経験がない方や資格取得後の就職サポートなどを期待するときは通信教育など別のサービスを遣唐した方がよいでしょう。
心理カウンセラーになる最短ルートは通信講座!
結論をお伝えすると、心理カウンセラーになる最短ルートとしておすすめなのは「通信教育」です。
通信講座の最大のメリットは、自分のペースでどこでも学べる自由さにあります。仕事や家庭の都合で通学が難しい方でも空いた時間を活用して効率よく学習したり、大学や専門学校と並行して利用したりすることも可能です。
また、通信講座は専門知識をコンパクトにまとめているため、無駄なく心理学の基礎から応用までを学べるのも魅力として注目されました。通学型のスクールと比べて費用も比較的安く抑えられる傾向にあり、経済的な負担を軽減できるのもポイントです。
短期集中型で心理カウンセラーを目指したい方は、ぜひ通信教育の利用を検討してみましょう。サポート体制が整ったスクールを選べば、質問対応や就職相談なども充実しています。
心理カウンセラーに向いている人の特徴とは?

共感力が高い
共感力とは、相手の感情や立場に深く理解を示し、それを感じ取る力です。単なる「同情」や「同意」ではなく、相手の世界をそのまま受け取り、心に寄り添うことを意味します。
カウンセリングをする際は、相手に「この人は自分を理解してくれている」と思ってもらうことが大切です。安心感や信頼感がその後のカウンセリング効果にも表れるため、「評価・アドバイス」ではなく「理解・受容」を伝えるよう意識しましょう。
反対に、共感力が低いまま心理カウンセラーになると、相手は「分かってもらえていない」と感じて心を閉ざしてしまいます。表面的な会話に終始し、本音を引き出せないなど、双方にとってメリットがありません。
論理性がある
論理性とは、情報を整理し、因果関係や構造を明確に捉えながら筋道立てて考える力のことです。心理カウンセラーに論理性があると、感情や直感に流されることなく、物事を冷静かつ客観的に判断しやすくなります。
また、相手の話の中から問題の背景や構造を整理して把握したり、何が課題なのかを見極めたりしやすいのもポイントです。問題点がわかれば適切なアプローチも見つかりやすく、カウンセリングのプロセスが計画的に進みます。
反対に、論理性がないと話の内容を感情で受けてしまい、心理カウンセラー自身が混乱する可能性があるので注意しましょう。問題の見立てや対応方針があいまいになりやすく、支援の質が下がってしまいます。
忍耐力がある
忍耐力とは、思い通りにいかない状況でも感情的にならずに待ち、粘り強く対応する力です。
心理カウンセラーは「すぐに答えを出せない」状況に直面することが多く、時には「相手がなかなか心を開かない」「同じトラブルが何度も繰り返される」ということも考えられます。相手のペースを無視して「急がせる」ような関わりになると、表面的な対応になってしまうので注意しましょう。
反対に、「変化には時間がかかる」ことを理論的に理解して、長期的な視点で物事に取り組める人は心理カウンセラーに向いています。少しずつの変化で焦る気持ちが出ることもありますが、人の変化を見守るのが苦ではない人であれば天職となるでしょう。
価値観の違いを受け入れられる
「価値観の違いを受け入れる」こととは、自分とは異なる考え方・信条・生き方を否定せず、理解しようとする姿勢を持つことでもあります。
心理カウンセラーの場合、自分の感覚では「理解できない」「納得できない」と感じることであっても、相手の立場に敬意を持って接する必要があります。自分の価値観を押しつけず、相手の「そのままの在り方」を尊重できれば、少しずつ信頼感を築けるでしょう。
「価値観を受け入れる=同意・肯定する」と思われがちですが、必ずしも賛成したり好きになったりする必要はありません。その人の視点に立って理解しようと努力し、相手を「矯正しよう」と思わないことが、心理カウンセラーに必要な要素です。
心理カウンセラーになるには国家資格が必要?

心理カウンセラーになるために、国家資格は必須ではありません。「心理カウンセラー」という名称自体は資格がなくても名乗ることができ、医師・弁護士・栄養士・キャリアカウンセラーのような「名称独占資格」ではないこともポイントです。
心理カウンセラーの資格にも国家資格と民間資格とが存在しますが、どちらを持っていても同じ「心理カウンセラー」を名乗れます。
ただし、資格の有無で就職のしやすさやできる業務範囲は大きく異なることが多いです。例えば、病院・学校・公的機関などの場合、国家資格のある心理カウンセラーが優遇される傾向にあります。資格がないと就職先が民間のカウンセリングルームやフリーランスなどに限られがちで、信用・信頼が足りないと感じるかもしれません。
本格的に心理カウンセラーを目指すなら、国家資格を取得することがおすすめです。公認心理士や臨床心理士の資格があると、キャリアの選択肢も広がります。
心理カウンセラーになるためのおすすめ資格一覧

公認心理師
公認心理師は2017年に誕生した日本初の心理職国家資格です。国家資格として社会的認知度も高く、医療機関や公的機関での採用で有利になります。
取得方法・難易度
取得には大学で指定科目を履修後、大学院進学または2年以上の実務経験を経て国家試験に合格する必要があります。試験の合格率は約70%程度と比較的高いものの、受験資格を得るハードルが高いのが特徴です。
臨床心理士
臨床心理士は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する民間資格ですが、心理関連で最も歴史ある資格で、社会的認知度も高いです。
特に学校のスクールカウンセラーとして必要な心理専門職に認定されているため、教育分野での需要が高いです。
取得方法・難易度
取得には指定大学院修了が基本要件で、資格試験の合格率は約65%程度です。公認心理師と並び、プロの心理カウンセラーとして最も信頼される資格です。
参考:スクールカウンセラー等活用事業実施要領(令和6年一部改正)|文部科学省
産業カウンセラー
産業カウンセラーは一般社団法人日本産業カウンセラー協会が認定する民間資格で、主に企業や組織で働く人々のメンタルヘルスケアを担当します。
メンタルヘルス対策、キャリア形成支援、職場環境改善という3つの活動領域があり、企業の健康経営推進に貢献する専門家として注目されています。
取得方法・おすすめの人
資格取得には協会の養成講座(約140時間)を修了するか、指定の大学・大学院で心理学関連科目を履修する必要があります。一般的な心理カウンセラーと比べて「職場」に特化しているため、企業内で活躍したい方や、産業・労働分野に興味がある方におすすめの資格です。
メンタル士心理カウンセラー®
メンタル士心理カウンセラー®は日本メディカル心理セラピー協会(JAAMP)が認定する民間資格です。心理学の基礎知識やストレスによる症状とそのケア方法などを修得し、人間関係や心の問題で悩む方をサポートする心のスペシャリストとして認定されます。
取得方法・おすすめの人
通信講座で学習でき、在宅での受験が可能なため、社会人や主婦の方でも無理なく取得できるのが魅力です。学歴や年齢の制限もなく、約2〜3ヶ月で資格取得が可能なため、心理カウンセラーを目指す最初のステップとして人気があります。基礎的な心理カウンセリングのスキルを身につけたい方や、短期間で資格取得を目指す方におすすめです。
参考:メンタル士心理カウンセラー®資格(メンタル心理資格)認定試験
メンタル心理インストラクター®
メンタル心理インストラクター®は日本インストラクター技術協会(JIA)が認定する民間資格です。心理学やカウンセリングの専門知識に加え、医療知識も学べる資格で、心の問題を抱える人とその家族へのサポート方法や社会復帰に向けた生活改善方法などを理解した人材として認定されます。
取得方法・おすすめの人
通信講座で学べ、在宅受験が可能なため、働きながらでも資格取得を目指せます。心理学の基礎からメンタルヘルスケアの実践的な知識まで幅広く学べるのが特徴で、職場や地域、家庭など様々な場面で活用できるスキルを習得できます。心理学を学び始めたい方に適した入門レベルの資格です。
子供心理カウンセラー
子供心理カウンセラーは日本インストラクター技術協会(JIA)が認定する民間資格です。子どもの心理や発達に関する専門知識を持ち、子どもとその保護者に適切なカウンセリングやアドバイスを提供できる人材として認定されます。
取得方法・おすすめの人
通信講座で学習でき、在宅受験に対応しているため、子育て中の方や教育関係者でも無理なく資格取得を目指せます。教育現場や児童福祉施設で活動したい方、子育て支援に関わりたい方におすすめの資格です。
チャイルド心理カウンセラー
チャイルド心理カウンセラーは日本メディカル心理セラピー協会(JAAMP)が認定する民間資格です。子どもの心理や発達を理解し、子どもの悩みや問題に対してカウンセリングを行う技能と知識を持つ専門家として認定されます。
取得方法・おすすめの人
通信講座で学習でき、在宅での受験が可能なため、仕事や家事と両立しながら資格取得を目指せます。主に保育や教育の現場、子育て支援センター、児童福祉施設などで活用できるスキルを習得でき、子どもの心理に特化したカウンセラーを目指す方に適しています。
福祉心理カウンセラー
福祉心理カウンセラーは日本メディカル心理セラピー協会(JAAMP)が認定する民間資格です。高齢者、障がい者、児童などの福祉分野で心理的サポートを提供する専門家として認定されます。
取得方法・おすすめの人
通信講座で学習でき、在宅での受験に対応しているため、福祉関係者や医療従事者など、既に仕事をしている方でも無理なく資格取得を目指せます。福祉と心理学の両分野に興味がある方におすすめの資格です。
メンタルヘルス・マネジメント®検定
メンタルヘルス・マネジメント®検定は大阪商工会議所が主催し、日本商工会議所が後援する公的検定試験です。職場におけるメンタルヘルス対策の知識を証明する資格で、Ⅲ種(セルフケア)、Ⅱ種(ラインケア)、Ⅰ種(マスターコース)の3段階に分かれているのが特徴です。
取得方法・おすすめの人
受験資格は不問で、同日に複数コースの受験も可能です。合格率はⅢ種・Ⅱ種が約70%、Ⅰ種は約20%と難易度に差があります。企業でのキャリアアップや産業カウンセラーを目指す方におすすめです。
教育カウンセラー
教育カウンセラーはNPO法人日本教育カウンセラー協会が認定する民間資格で、学校現場で児童・生徒の心理的サポートを行う専門家として認定されます。
初級・中級・上級の3段階があり、カウンセリングの知識を学級経営や授業、生徒指導、保護者対応などに活かすスキルを習得します。
取得方法・おすすめの人
資格取得には協会の養成講座修了と実践経験が必要で、教員や教育関係者を中心に取得されています。特に初級は2日間程度の講座受講で取得可能なため、教育現場での心理支援に関心がある方の入門資格としておすすめです。
心理カウンセラーに関するよくある質問

心理カウンセラーは「仕事ない」「きつい」と言われるけど本当?
心理カウンセラーは「仕事がない」「きつい」との意見が特にインターネット上で言われることがあります。
実際、確かに公認心理師や臨床心理士などの高度な資格を持つ人材の需要は高いものの、正規雇用の求人数は限られており、非常勤やパートタイムの形態が多いのが現状です。
それに加え、クライアントの深刻な悩みに向き合い続けることで生じる「共感疲労」や、成果が見えにくい仕事特性からくるストレスも存在します。
近年はメンタルヘルス重視の社会的傾向から需要は拡大傾向にあり、特定分野での専門性を高めたり、複数の職場を掛け持ちしたりすることで安定した働き方は十分実現可能になっています。
心理カウンセラーになるには何が必要ですか?
心理カウンセラーになるために最も重要なのは、心理学の専門知識とカウンセリングスキルの習得です。
これらは大学・大学院での学習、専門学校や通信講座での資格取得、実務経験などを通して身につけていきます。
資格取得はその証明となりますが、資格だけでなく継続的な学習や自己研鑽も欠かせません。また、クライアントの悩みに共感する力、適切な距離感を保ちながら支援する判断力、守秘義務を守る倫理観なども重要です。
心理カウンセラーになるにはどんな学歴が必要ですか?
心理カウンセラーになるために絶対必要な学歴はなく、高卒や中卒でも目指すことは可能です。
ただし、目指す職場や取得したい資格によって必要な学歴は異なります。
公認心理師や臨床心理士などの高度な資格を取得するには、大学で心理学関連の指定科目を履修し、さらに大学院に進学する必要があります。
一方、メンタル士心理カウンセラー®や子供心理カウンセラーなどの民間資格は学歴不問で、通信講座などで学んで取得できます。
心理カウンセラーになるのは難しいですか?
心理カウンセラーになること自体の難易度は、目指すレベルや分野によって大きく異なります。
公認心理師や臨床心理士などの高度な資格を取得し、医療機関や教育機関で専門家として働くことを目指す場合は、大学・大学院での長期的な学習と厳しい試験突破が必要なため、かなり難易度が高いといえます。
一方、民間資格を取得して企業や個人向けにカウンセリングサービスを提供する場合は、比較的短期間で始められます。ただし、どのレベルでも専門知識の習得と実践的なスキルの訓練は必須で、人の心に寄り添う仕事として継続的な学びや自己成長が求められます。
まとめ
心理カウンセラーになるためには複数のルートがあり、大学・大学院で学ぶ正統派ルート、専門学校や通信教育で学ぶ実践的ルート、社会人からチャレンジする最短ルートなど、自分の状況に合わせた方法を選ぶことができます。
資格は法的に必須ではありませんが、専門性の証明として重要で、目指す分野に応じた資格取得がおすすめです。公認心理師や臨床心理士といった高度な資格から、メンタル士心理カウンセラー®などの比較的取得しやすい民間資格まで、様々な選択肢があります。
心理カウンセラーの仕事は決して楽ではありませんが、人の心に寄り添い支援することにやりがいを感じる方にとって、大きな満足感が得られる仕事です。まずは自分の状況と目標に合わせた資格取得から第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
- 通信講座のSARAスクール編集部
-
心理カウンセラー資格やリンパケアセラピスト等の体系資格、食育資格などを扱うSARAスクール編集部が運営するコラムです。主に女性向けのキャリアアップやスキル習得を目的とした講座が多く、家事や育児と両立しながら学べる環境が整っています。資格取得を目的とした講座も充実しており、仕事や日常生活に活かすことが可能です。